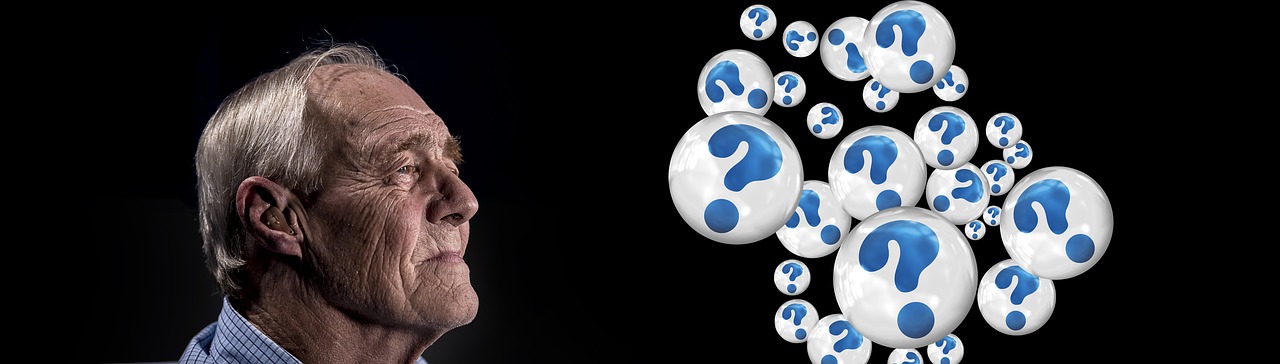「ラグビーを哲学する」のシリーズは、多くの哲学思想にラグビーを当てはめて考えようとする試みです。ラグビーの本質をよく知ることにもなりますが、同時に哲学のおさらいになり、普段の生活を見直してみることにもつながっていくかなと思っています。
1、サルトルについて
1)不遇の少年青年時代
1905年にパリで生まれますが、1歳で父が病死、祖父の家で育てられます。3歳の頃右目の視力をなくし、強度の斜視となります。転向したラロッシェル(ラグビーファンならご存知の田舎街、今年ハイネッケンカップ準優勝、国内選手権も準優勝の快挙)の学校には馴染めませんでした。容姿が元で仲間から辛い思いをしたり、初恋の相手にも見放されたりしています。この容姿のコンプレックスが、他人の目、まなざし、ということの意味を掘り下げる様な哲学的思考の根っこになっている様に思えます、それでも学業は優秀で高等師範学校に進学します。しかし、楽勝で合格と思われた最難関のアグレシオン試験(教員試験)に不合格になってしまいます。(理由は不明ですが、サルトルの革新的な思考内容に、審査官がついてこれなかったのではないかと思います)
2)回ってきた運
この試験に落ちたことで逆にサルトルに運が回ってきます(無神論者のサルトルに運が回るなんて書くのは失敬ですが)。生涯のパートナーとなるボーヴォワール(のちに「第二の性」などを執筆します)とも知りあいます。1年後のアグレガシオン試験では主席がサルトル、次席がボーヴォワールでした。そして二人はかつてない様な今でもぶっ飛んだ契約婚をします。お互いに偶然の恋愛は自由、子供は作らない、契約時間は2年毎に更新という前衛的、画期的な結婚生活です。(その結婚生活はサルトルが亡くなるまで50年近く契約更新を重ねて続きました)
そして1931年に「嘔吐」を発表、これがベストセラーになります。実存主義を描いた小説です。
3)戦争、実存主義のスーパースター
第二次大戦ではフランスはナチに降伏し、占領下におかれます。サルトル はレジスタンスに身をおます。カミュとはこのレジスタンス時代に知り合いました。
戦後のパリでは、若者の多くは戦争の虚しさから虚無感に落ち入り、信じるものがなくなり、サンジェルマンの酒場にたむろしているだけの状態でした。そう言った若者たちを「実存主義者」とマスコミは名付けたのです。
そんな中、実存主義のサルトルが「実存はヒューマニズムか」という講演をするという噂が飛び交います。噂は噂を呼び狭い店の中はすし詰め状態で、、外にも入れない人が道路に溢れで出ました。翌日の新聞では、一夜にして時代の寵児となっったと報道されました。
その講演は 著書「実存主義とは何か」に収められました。
その中の言葉「実存は本質に先立つ」は実存主義を象徴する言葉として有名で代名詞になっています。サルトルは実存主義の時代の寵児として、戦後から60年代にかけて若者の支持を受けて、マルキシストや哲学界のスーパースターでした。日本でもサルトルの「実存主義とは何か」は300万部を超えるベストセラーになりました。
4)カミュ論争、構造主義からの攻撃
「反体制のシンボル」、「権力に迎合しない」
実存主義の生き方として、アンガージュマンを説くサルトルは、サルトル自身その様に見られる自分を受け入れ、演じていたのかもしれません。
その結果、非暴力主義の旧友カミュを「不条理と言いながら現実に甘んじているだけだ」と批判します。カミュはそれに対し反論はしませんでしたが、「実存と言いながら欧州中心の進歩的歴史観の構造にとらわれている」、そうレヴィ=ストロースに「野性の思考(1962年)」で非難指摘され、大論争になります。要するに神を否定したサルトルは唯物史観が神の様になってしまっていると批判したのです。 サルトルは構造主義を「ブルジョア的なイデオロギーの障害だ」と反発します。サルトル の持つ歴史観を問われたのに、その歴史観を振りかざして反論してしまった結果、これは完全にサルトルの敗北でした。そうして、欧米では実続主義は終わりを告げたかの様になり、代わりにレヴィ=ストロースが時代の寵児に躍り出て、構造主義の時代が幕を開けることになります。
5)ノーベル文学賞を辞退、思想の実践を貫く
1964年ノーベル文学賞を受賞しますが、キッパリ辞退します。実存主義者のサルトルとしては、自分の立場や評価は他人が決めるのではなく、自分が決めることにこそ意味があるのです。その鉄学を貫いた当然の結果ででした。
その後も左派の知識人、マルクス主義の擁護者としての立場を貫き、世界各地を回って活動します。革命のキューバ、東欧、日本をパートナーのボーヴォワールとそもに訪問しどこでも熱狂で出迎えられました。
パリ市内での葬儀には5万人が集まったと言います。中には構造主義者のミシェルフーコーの姿もありました。
3、サルトル の思想について
サルトル は無神論者で実存主義者でマルクス主義者です。
神については戯曲でコテンパンに
「実存は本質に先立つ」これはよくペーパーナイフの例で説明されます。ペーパーナイフは紙を切るという本質が先にあって、ペーパーナイフができた。すなわち本質が存在に先立っているわけです。世の中の全てのものはこの様な本質が先立っている即時存在です。しかし人は生まれた時には何になるかわからない=本質がなんなのかはわからないのですが、その後の人生で自由な選択をすることで、自分自身の本質を掴んでいくものなのです。すなわち 「実存は本質に先立つのです。
その時、人は自分を見つめ直します(=対自存在)。対自存在とは「それがあるところのものではなくあらぬところのものである」ということ。自分を意識してこうありたいと思う姿です
どんなどんな選択肢を選ぶ決断をしようと自由なのですが、その決断によって様々な重荷を背負うことになります。「人は自由の刑に処されている」という言葉であわらしました。
もう一つの存在があります。それが他者の目から見た存在=対他存在です。
自分で選んだ道なのですが、いつの間にか他者のまなざしによって見られることで結論付けられ、即時存在になってしまっているのです。「地獄とは他人のことだ」。その時、自分の「まなざし」をその人に向けることで、見られるものから見るものへと主体は変化します。即時存在から逃れることができます。
71年のハードロックの幕開けの名曲、ユーライヤヒープの「対自核」を思いまします。当時中学生だった私にはこの難解な邦題になぜか惹かれました。曲は単純明快なのですが、、、。 最初の歌い出しがこうだったです。 逃げるお前を見ているぞ お前は何から逃げるのか 怖がることはない ただおまえ自身を見つめてみろ
サルトルはアンガージュマン(英語でエンゲージ)が大切だと言います。アンガージュマンは社会参加と訳されることが多いですが、もっと広い内容を持っています。自分が置かれた状況に自らを積極的に身を投げ出し(投機し)、自ら自分自身を拘束していくことを選択することです。
人が外の存在特に社会に積極的に関わりを持つことで、世の中はより良くなっていくものです。サルトル は社会参加として、マルクス主義者として活動します。
3、山沢の中にサルトル を見た
ラグビー日本代表候補の、山沢拓也のことを考えさせられました。
山沢拓也は自由を求めます。数十種のキックを蹴りわけ、サッカーばりのドリブルをし、キックとみせて、鋭いステップ、相手を翻弄しまくります。神出鬼没、変幻自在、見た目に自由なラグビー です。
しかし、今回取り上げるのは山沢の日本代表をめぐる一人のラグビープレーヤーとしての「選択」の話です。サルトル の実存主義の様に、山沢は自ら選択して、自己の周りからの目を裏切ります。どの様なラグビー をするのかを、決めるのは自分であって、周りから枠にはまった評価をされるの自ら拒否します。それこそが山沢の自由なのです。
山佐拓也に注がれるファンの「まなざし」は、「日本代表を掴み取れ」「というものです」、その「まなざし」に山沢は「そんなんじゃない」という「まなざし」を逆に向けることで、その「まなざし」から逃れたのです。
また、日本代表ヘッドコーチジョセフの「まなざし」は、「山沢のラグビー は今の日本代表にはフィットしない。」というものです。現在のジョセフの日本代表のチーム作りには、ある程度の確実性が望まれます。チームメイトの松田力也の様なタイプです。それは山沢にはわかっています。しかし山沢は逆にそんなジョセフに「まなざし」を返します。「そんなもんじゃない」と。その様なラグビー の枠にとどまることを拒否しました。あくまで、ラグビー の本質は、創造性であり、それをピッチ上で表現することこそが、山沢の求める最高のラグビー なのです。
今回6月12日のサンウルブスの先発に選ばれることで、山沢の中で様々な葛藤は消えました。その条件は全て揃いました。これを仕組んだのはアシスタンとコーチに入った沢木氏です。沢木は山沢に自由にやらせました。最も1回限りの急造チームでは、それ以外の選択はなかったかもしれません。そして山沢自身の中で 対自存在と沢木や急造サンウルブスというチームからの対他存在が一致したのです。
その結果が12日静岡のジャパンVSサンウブス戦の山沢のプレーに現れたのです。このゲームで、まさに水を得た魚の様に山沢は自分の能力を発揮し、ジャパンをきりきりまいさせてしまいます。キックオフから10Mラインギリギリに落とし、挨拶代わりに、大外への絶妙の飛ばしパスから始り、キックでジャパンの出足を止め、裏へのごろパンを蹴りわけ、ルーズボールに足技Wを絡ませ、トライを縁出します。さらには、ドロップゴールまで狙ってしまいます。八面六臂の活躍です。
このことは山沢にとっては、今回のジャパン候補からの決別を意味します。
プレーが自由なだけでなく、ラグビー人生も自由です。周りから勝手な見方をされることを拒否します。自分で決めた自由なラグビーを貫きます。それが山沢拓也の自由なのです。
山沢の中にサルトル を見ました。
サルトル も容姿のコンプレックスからのまなざしを跳ね除け、アンガージュマンにいきつき、実存主義者でマルクス主義者という、その人生をまっとうしました。
山沢も「話すことがあまり得意でない」という苦手意識が、「言葉でなくプレーで自分の自由を表現する」と言う道を選ばさせたのかもしれません。
山沢の様なスタンドオフが自由に活躍できる日本代表チームが出来上がるときは、日本のラグビーがかなり成熟してきた時になると思います。まだまだ日本のラグビーはその域にはありません。