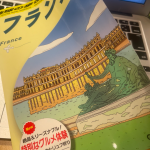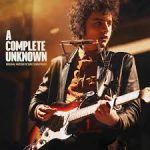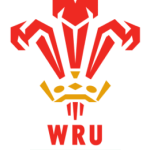昨年と同様の決勝戦となった。
場所はユタ州、ソルトレイクシティ。日本時間21日朝10:30キックオフ
ソルトレイクは先日のチャーリーカークの狙撃事件があった街である。しかもその後アメリカの分断が深刻敵状況になっている。少しでもリベラルを養護するような発言をしようものなら、反対派から集中攻撃を受け、役職や会社を解雇されるケースが止まらない。もはや民主国家と言えない野蛮な国であるといってもおかしくない。すでに内戦状態にあるという専門家もいるほどだ。合理的且つ短絡的に、白か黒か、敵か味方かをはっきりしたがる国民性である。銃こそが敵から身を守る手段として容認どころか奨励さえされてる。
ラグビーのような曖昧で、ゲームが終わってさらに仲良く出来るような文化が、アメリカ社会で育たないという理由の根本がそこにあると感じる。2031年のW杯開催のときのアメリカはどんな状況になっているのだろう、心配である。
話を決勝戦にもどそう
フィジーはランキング9位、ジャパンはランキング13位である。
ジャパンはこの試合に勝てば一時的にランキング11位に浮上できる
しかし、ジャパンはフィジーのようなチームを苦手にしており、フィジーとの対戦成績は4勝16敗。最後にジャパンがフィジーに勝ったのは、2019年釜石でのW杯のウォームアップマッチだった(松島や福岡のトライを覚えている}。
昨年はPNCの決勝で顔をあわせ17−41と大敗してる。その時のジャパンは超速ラグビーを消化しきれず、課題満載だった。主な課題は、キャプテンシー、ゲームコントロール、ディフェンス、キックの使い方などである
1)その試合、若手中心の中ペテランの立川がSOを努めていた。しかし、その立川が後半に交代すると、立て続けに4トライを取られ、渡してしまった流れを戻せなかった。今年はディアンズがキャプテンとして1試合ごとに成長をみせている。キャプテンとして体を張って局面を打開するプレーは頼りがいがある。ディアンズはこのまま成長できれは、10年はキャプテンの心配は無いだろう。
2)さらに今年は、ディフェンスの精度が上がっている。タックルの成功率が90%をこえている。これは組織的なノミネートが機能していることの現れである。ディフェンスの連携ポカミスによる失トライは少なくなった。練習とコーチングの成果である。
3)80分間のゲームコントロールができている。むやみやたらに「超速ラグビー」で攻めまくるのではなく、キックをつかってエリアをとるプレーを的確に織り交ぜている。ボディブローで相手の消耗をさそうという作戦も取れるようになってきた。
4)若手の成長である。江原、佐藤、小林、広瀬らがテストマッチの経験を積み重ね、戦力としての計算できるようになりつつある。これは長期的視野をもった組織マネージメントの成果である。
5)セットプレーから一発でトライを取れるようなサインプレーの切れがあり、重要な得点源になっていいる。これもコーチングとトレーニングの成果である。おそらく、まだまだたくさんの隠し玉があり、フィジー戦はまた、新しいムーブからのトライが見たいものである。
6)しかし残ったままの課題はまだある。一つがゴール前フィジカルで攻められたときのディフェンスである。今回ガンターの欠場が穴とならないと良いのだが…..。もう一つがコンテストキックの処理である。弾いたボールが相手に入ってしまうことが多い、これまで石田、グリーンも頑張って入るがいまいちと言わざるをえない。今回かわった木田、中楠がどこまでクリーンに確保できるかがが注目される。
一方のフィジーのメンバーをみると、1列めのマウイ、イカニベレは昨年も出ていた。3番ドゲはカナダ戦2つのイエローでレッドになりながらも今回出場を認められている。4番5番のロック陣も昨年の花園の出場している。スクラム、セットプレーはフィジーが優勢となりかねない。
ハーフ陣はSHロマニ、SOムンツから、クルボリ、ムンツに変更になっている。ムンツ冷静なゲームコントロールが最近のフィジーのラグビーを知性的で理にかなったものにしている。しかも、強烈なドミナントタックルも狙っている。要注意である。センターは今季静岡に加入のランドラドラがフィジ代表に合流していないので、13番東芝のタマニバルが先発と予想してはいたが、今回好調なラブラボウは先発。そのラブラボウはカナダ戦で複数のトライも上げマンオブザマッッチになっている逸材でありこちらも安心はできない。。
フィジーの特徴は、長い手足をつかった自由奔放なラグビーであり、オフロードの多さが際立ってる。しかも一人ひとりのフィジカリティが高く、簡単には倒れない。ジャパンは倒しきれなくともダブルタックルで2人めがボールに絡むようなディフェンスを仕掛けねばならない。もしくは、パスコースに入って、フィジーに無理なパスをほうらせるようなディフェンスも有効であろう。しかし、これは入れ違ってしまう危険性、さらにデリバリーノックジョンの反則の危険性と隣り合わせである。その点、長田ならパスカットのタイミングを心得ており、まるで南アのコルビのようなここぞのときにインターセプトも決められるかもしれない。
フィジーの弱点は、好調不調のムラのある点につきる。これは国民性からくるのかのしれないが、調子に乗らせれば止まらないが、不調だと雑になり、諦めも早くなる。ジャパンはフィジーにフラストレーションを澑めさせるようなラグビーをさせれば勝機がでてくる。セットプレーでのレフリングを味方にすることや、攻め込まれてもフィジーのミスで終わらせるなどである。前半はクロスゲームでも良いが、前半最後にはジャパンは得点をあげ、少なくとも10点差以上をつけ、後半最初の得点もジャパンが取ることができれば、フィジーのラグビーは雑になり、無理なパスやオフサイド、ハイタックルなどの反則も増えてくるはずである。
「このようにキックで相手の裏、無理に攻めさせるが、トライまでさせずミスで終わらせる。ボールを奪いキックでエリアをとる(50−22が最高)。ラインアウトからのサインプレーで得点を重ねる。フィジーはイライラし反則が増える。李舜臣のPGでじわじわ得点を引き離す」
こういった勝ちパターンのゲームになれば最高である。
また、課題だった、ゴール前まで攻め込まれての、モールやフィジカルアタックへの対応。コンテストキックのキャッチング、こぼれボールへの働きかけ、この面での成長が見られるゲームを期待したい。