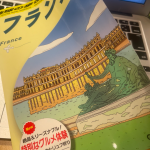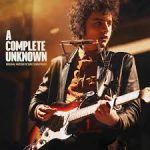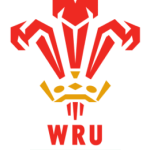フィジー トンガ
日本時間30日12時キックオフ、フィジースパ
32−10
前節でひさびさに格上のサモアを破って勢いのあるトンガが、日本でもおなじみのSHオーガスティンプルのトライで先制。さらにPGで0−7とリードを広げる。
しかし、そのあとフィジーはPGで手堅く点をかえす。トンガナンバー8MATAがイエローの間に日本でもおなじみのセタタマニマルにトライが生まれ、10−7と逆転さらにトライを追加しフィジーペースと思われたが、攻めあぐむフィジー。終了間際にトンガがPGを返し、前半は17−10と僅差で終了。
後半は一方的にフィジーがせめ、トンガMATAも2枚目のイエローで退場。終わってみれば32−10とボーナスポイントをとってのFIJIの勝利だった。
しかし、フィジーはスクラム、フィジカルでトンガを圧倒し、攻め方しだいでは、もっと得点差をが開くような実力差があった。
フィジーは7月のスコットランド戦以来のゲームであり、前半はゲーム間隔があきすぎてエンジンがかかるのが遅くなった感がある。
このゲームのアシスタントレフリーは日本の滑川さん、古瀬さんが努めた。
フィジーはエースのツイソバは欧州のクラブ事情で出ていない。4名が初キャップという布陣であった。
来週は、フィジーがサモアの地に乗り込む。
ジャパンーカナダ
前半ラインアウトからの左展開でいきなりチャンスを迎え、ゴール前スクラムでFKをもらったジャパンがいきなりトライをあげる。さらに新ディアンズキャプテンはゴール前のペナルティからPGを狙う選択をして10−0と引き離す。
しかし、ここから突如ジャパンのオフサイドの反則が止まらなくなる。トライとPGを決められ10−10の同点。しかも、反則の連続からララトゥブアにイエローが出てしまう。この20分近くは試練であった。
しかし、前半終了間際にはなんとかキャプテン自らのトライで流れを引き戻した。
後半は、長田を投入してバックスが安定。さらに1列目も入れ替えるとスクラムも優位になり、一方的な展開に持ち込んだ。
戦前ジャパンの課題は3つあった。
1,リーチの居ない間のキャプテンシー(ゲームコントロール含め)
2,ハイボールの処理
3,ディフェンスの連携
1,については、ディアンズは素晴らしい経験ができた。同じ反則の連続というあまりありえない状況にどう対処するかである。今回はうまく対処できたかというとそうでもない。レフリーとのコミュニケーションをもう少し早く実行し、チームへ対策の落とし込みをできたはずだった。テストマッチでは色々なことは起こるのでキャプテンとしての経験を積むしか無い。今回の一番の収穫はディアンズがこの苦しい体験をできたことであろう。
2,については、まだまだ課題が多い。ここがジャパンの弱点であることが知れ渡ってしまっている。世界中どのチームもコンテントキックを狙ってくる。落下点ででのペナルティも2度ほどあり、まったく解決できていない。
3,今回ディフェンスでの連携ミスはなかった。その機会がなかっただけかもししれない。良かった点は、タックルの精度であって、106回のタックルで成功率は92%であった。ミスタックルは10回以下である。まずかったのはモールディフェンスでカナダの3つのトライはすべてモールからのものであった。モールディフェンスのアングルの統制の乱れが生じている。
その他、今回の予想では、カナダのラインアウトが予想以上の出来だったことである。それに加えジャパンのラインアウトは安定していなかった。ジャパンのプレーの選択でもラインアウトではなく、スクラムの選択がおおかった。これはゲームプランだったのかピッチ上の判断だったのだろうか
ジャパンの最後のラインアウトからのムーブは完全に決まった。スローワーの佐藤くんがリターンボールを引っ張って切れ込んだ14番に渡すというものだった。
前半キックオフ直後のプレーもそうだが、ラインアウトが決まれはさまざまな形でのトライの可能性が高くなる。
良かったのは今回先発のグリーン、小林、佐藤、広瀬という初キャップ組がいきいきとプレーして輝いていたことである。
これで、来週USA戦に勝てば、相手はトンガになる可能性が高くなった。