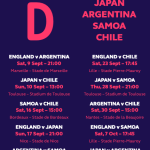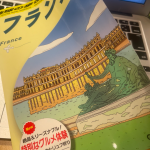ラグビーの連続攻撃。いわゆるアタックのフェイズを重ねていく。速い球出しから、コンタクト、ラック形成して、また速い玉だしを行う。ディフェンスも必死で反則をせずに守る。フェーズが途切れずに重なっていく。
そこに、そこはかとないグルーブ感を感じる。
「グルーブ」とは音楽用語である。
簡単に表現すると「ノリノリ」の様な状態。思わず体が動き出す様な状態である。
音楽では同じリズムを執拗に繰り返すことで生み出されてくる。譜面通りのかっちりとして縦割りの演奏ではこのうねりは出てこない。そこにはシンコペーションも多用され、微妙なリズムのズレがうねりとなってくる。このうねりは主にドラムとベース、リズム隊のコンビネーションで生み出される。ベースとバスドラは同期し、突っ込み気味にリズムの頭をリードしていき、そこにスネアドラムがややタメを作ってアクセントとしてのインパクトを与える。これを続けることでうねりが生じでグルーブが生まれるのだ。素晴らしいグルーブは例を挙げればキリはないが、60年代のアトランティックソウルのウィルソンピケットやオーティスレディングのバックを務めたドナルドダックダンとアルジョンソンのコンビ、さらにはモータウンのバックを務めたファンクブラザーズ(ジェイムスジェマーソン)などの演奏がその走りではないかと思われる。80年代では、スタジオミュージシャンの集まりでクロスオーバーバンドSTUFFの、リチャードティーの左手のピアノとドラムのスティーブガットの作り出すグルーブも素晴らしい。
ラグビーでも同様である。ラックからスクラムハーフが素早くパスアウトし、ファーストレシバーはワンパスでクラッシュしたり、時に微妙なためを作ってパスを放つ。そしてクラッシュしてラック形成からまた素早くパスアウトをして攻撃を続ける。まさにこれこそバンドのベースマンとドラマーのコンビネーションの作り出すグルーブである。
実はこの繰り返しはディフェンスもやりやすい。ディフェンスもこのグルーブのリズムに一緒に乗ってしまえば良いのだ。ディフェンスもこのグルーブに乗ってしまうと、ディフェンス側にもグルーブが形成される。そうなると、プレーは継続する。そしてフェイズが10、20と重なっていくと見ている側も心地よい。
しかし、このグルーブはいつまでも続かない。いつかは破綻する。実はその中でどちらが主導権を取るかの熾烈な争いが行われているのだ。それは、どちらのサイドが踊っているのか踊らされているのかだ。アタック側は相手を揺さぶり踊らさせて、穴を見つけたり、反則を誘ったりを仕掛ける。ディフェンス側も下さされているフリをしながた、実は相手を踊らさせて、ミスを誘ったり、ジャッカルのタイミングを見つけようとする。我慢比べでもある。
この緊張感が、ラグビーを見る目の越えた者にとってはたまらない。どちらが踊っているのか踊らされているのかの推理もまた楽しめる要素である。
ラグビーでグルーブ感の現れとしての例は、アタックとしては一昨年の神戸製鋼、日和佐篤とダンカーターのコンビネーションでのグルーブ。ディフェンスとしてはパナソニックのグルーブ。これらは