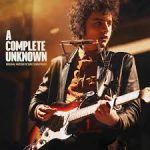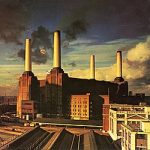1,はじめに
対抗戦が混戦になっている。
対抗戦Gは優勝をきめるものではなく、あくまでもどちらが強いかの対抗をするというポリシーがある(あった)のだが、近年は勝ち負けや大学選手権を重視するという世間の波にもまれて、ポイント制なるものが導入され、わかりやすく納得できるような順位付けがされている。そしてその順位で大学選手権の対戦枠が決まっている。1位抜けとなれば左の山にはいり有利になる。しかし、2位から4位までが右の山にひしめくことになり、順調にいけば、12月21日に2位と4位が正月の国立の座を争うということになるのである。
ポイント制は勝ちが5点、負けが1点、3トライ以上の差で勝てばBP1、7点差以内の負けでBP1、引き分けが双方3点となっている
2,現状と計算の前提
11月25日時点のポイントは
早稲田32P 残り7日 明治戦
明治 30P 残り7日 早稲田戦
筑波 28点 残り6日 青学戦
帝京 27P 残り30日 慶応戦
慶応 21P 残り30日 帝京戦
慶応は30日の帝京戦に6Pを取って快勝しても帝京は27Pとなるため、5位が決定。
筑波が青学には6Pをあげて勝つと思われるので34Pに伸ばすと仮定する。
しかし、その場合でも早稲田と明治のゲームで勝った方が点差に関わらず筑波を上回るので、明治もしくは早稲田の1位にけが決定する。この時点で1位抜けは早稲田が明治に絞られた。早稲田は引き分けでも1位抜けは確定する。
3,早明戦のBPのゆくえ
しかし、2位から4位の決定は、負けた場合にBPを取るかどうかが重要になる。
1)早稲田勝利の場合
早稲田 勝利 37Pもしくは38P
筑波 勝利 34P
明治 敗戦 32P もしくは33P
帝京 勝利 32P もしくは33P
明治と帝京がポイントで並んだ場合には当該チームの勝敗できまるので、明治がが有利だが、30日のゲームで帝京がBPをあげて勝利した場合。明治は負けても7点差以内でないと3位とはらない。
1位 早稲田 2位 筑波 (3位 帝京 4位 明治) 5位 慶応
21日の秩父宮は筑波ー帝京か筑波ー明治といった、帝京、明治にとっては対抗戦のリベンジとなるゲームとなる。
2)明治勝利の場合
早稲田 敗戦 33Pもしくは34P
筑波 勝利 34P
明治 勝利 35Pもしくは36P
帝京 勝利 32Pもしくは33P
明治はトライ数にかかわらず勝てば1位ぬけが決まる
早稲田は7点差以内の負けであれば、筑波と34Pでならぶことになるのだが、当該ゲームで勝利した早稲田が2位、筑波が3位となる。
早稲田が7点差以上の差で負けた場合は帝京の33Pと並ぶことになり、当該ゲームで勝利した帝京が3位、早稲田は4位になる。
早稲田7点差以内の負け
1位 明治 2位早稲田 3位筑波 4位帝京 5位慶応
早稲田7点差以上の負け
1位明治 2位筑波 3位帝京 4位早稲田 5位慶応
3)引き分けの場合
1位早稲田35P、2位筑波34P、3位明治33P 帝京32Pもしくは33P
帝京と明治が33Pでならんでも明治が本割で勝っているため順位はかわらない。
4,もしも筑波BPの前提がくずれたら
もし筑波が青学に勝ってもBPを取れなかった場合
早明戦に勝ったチームが1位ぬけは確実だが、2−3−4位の筑波、明治、帝京、もしくは、筑波、早稲田、帝京が33Pで並ぶ可能性がある。
筑波、明治、帝京が並んだ場合 筑波が明治、帝京に勝っており、明治は帝京に勝っているので2位筑波、3位明治、4位帝京の順になる
筑波、早稲田、帝京が並んだ場合。この3チームは3すくみになるので、その場合当該ゲームの獲得ポイントで順位が決定する
筑波は 早稲田戦、帝京戦で獲得は1+5の6ポイント
早稲田は筑波 帝京戦で6+2の8P
帝京は 筑波 早稲田戦で2+5の7P
したがって、早稲田2位、3位帝京 4位筑波の順になる