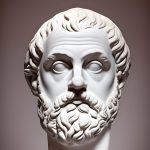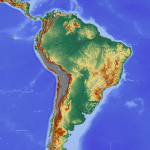ラグビーという競技は「利他」の競技にほかならない。自己犠牲というのとはちがう。ゲーム中はチームのためにプレーするなど意識すらしないものだ。それはもう当たり前過ぎで考えにもおよばない。逆にチームのためだということが出すぎてしまうとかえって失敗をすることになってしまう。
「利他」というのは、先々を考えずに思いがけずに行う行為が、あとから受け取り手の利になっているという現象である。何かを期待して行うとか、自分の利を計算して行うなどは利他とは言い難い。カントのいう「定言命法」である。
実は最近、トライ後の簡単なゴールキックが決まらないという現象が多発している。キックの名士松田力也、サントリーの高本などである。なんでもない中央のキックが横にそれたりしてしまっている。そこに必要以上の「利他」の感情が邪魔しているのではないかと推測する。
原因はもちろんキックカウンター60秒の採用である。
これまでは90秒だったが、ゲーム進行上から60秒に制限された。問題は60秒になったから時間が短くなり、焦ってルーティンが崩れるというのではない。全く逆である。キッカーは与えられた60秒をギリギリまで使おうとするあまりに、ルーティンを崩しているのである。したがって簡単な位置からのキックほどその可能性が高くなってしまってる。
なぜそうなるかというと、激しく戦う仲間のために少しでも休息の時間を与えたいとおもうからのである。これまではゴールキックの間、メンバーは一息つけるし、作戦などの意思統一もできたが、60秒ではそれも叶わないと「おれがなんとかしなければ」と思ってしまうわけだ。これが「利他」の考えがかというとそうではない。利他とは自然な行為で思いがけず行うことから生じる。この件では仲間のためというような余計な感情が入ってきてしまっているのである。キッカーの心理は微妙である。そこに狂いが生じている。
松田力也は今季ベイブリッツに移籍したばかりである。新チームのために貢献したいととう考えが出すぎてしまっているように思える。
もう一つの例
ラグビーはレフリーとの信頼関係でなりたっている。プレヤーはレフリーの立場、意思を尊重し、敬意をはらう。つまり自然な「利他」の関係になっているのである。たとえ見逃しや、ミスジャッジがあろうともそこは自然に目をつぶるものである。
しかし、だれとは言わないが問答無用でルールに厳しく高圧的なレフリングをおこなうレフリーがいる。そうなるとペナルティが少なくなるかというとそうではない。逆に反則の数も増えて、レフリーの目に見えないようなグレーや不正なプレーも増えてしまうのである。そんなゲームは荒れてしまう。
これは利他の意識が薄れることにある。
有名な行動経済学に「6つの保育園の話」というものがある。保護者は5時までのお迎えの約束であったが、仕事の都合などで約束を破る親が増えてきてしまった。そこで保育園側は5時以降にお迎えに来た親には罰則金を課すというルールを作った。そうすると逆に罰則金をはらってルールを平気でやぶる親御さんがどんどん増えてきてしまったというものだ。
これもそれまで目に見えないところにあった「利他」の意識が薄れたところにある。
シンビン(イエローカード)の採用や運用も、もとからラグビーにあった純粋な利他の意識をスポイルすることに繋がっていないかと心配になる。