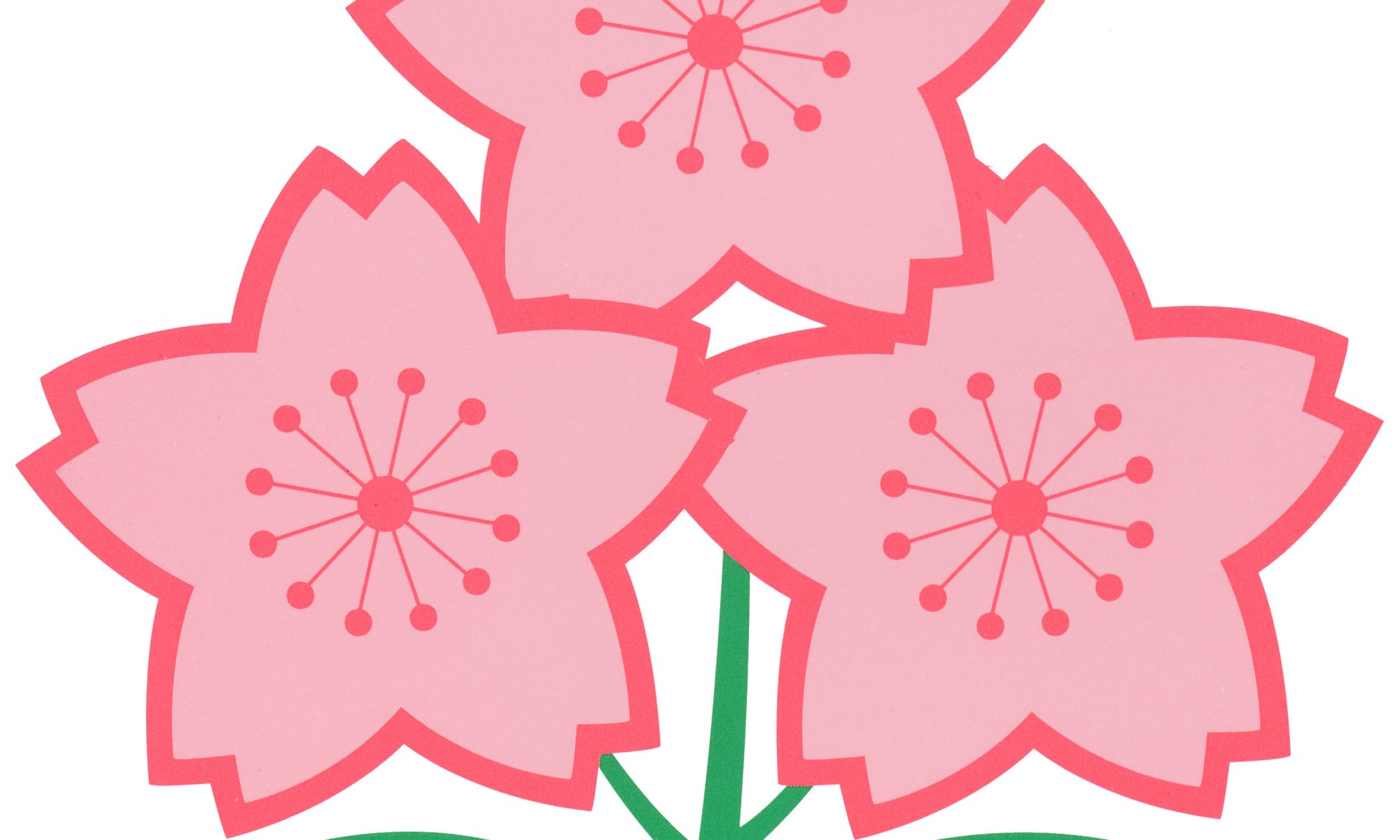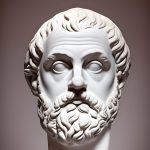期待のゲームだったが、大敗に終わった。
71−7 トライは11本対1本。
なぜこのような大差にになってしまったのか?
完全に実力差であることは間違いがない。
この日出出場した選手は、ジャパン本体の選手にけが人が出て、3番手4番手の選手としてこの合宿に急遽よばれた選手達が多かった。
したがって、代表レベルの国際ゲームの経験は薄い。インターナショナルフィジカルの強さに初めて対戦したメンバーも多い。昨年の夏の初々しいジャパンの姿を見ているようだった。現在のジャパン本体との経験や力の差は大きいはずだ。そしていい経験をしたはずだ。
しかし、それだけに終わらせていいのだろうか?
1,レフリングなどハプニングへの対応
一つはレフリングへの戸惑いであった。たしかにこの日のレフリングは異常だった。
というプレーがことごとくプレーオンになるレフリング。
私はかれこれ40年以上、小学生からワールドカップまでどのレベルのラグビーを年間30試合以上は見ているが、こんなに「(いわゆる)流す」レフリングは初めて見た。
このレフリーは、このように「流す」レフリングのほかにもスクラムの判定や、厳しすぎるイエロー、レッドカードの判定など疑問の笛も多かった。したかって、これは主審のレフリー個人の資質なのではなく、アシスタントやTMOも含めたゲームオフィシャル全体で作りあげられたものだった。
ゴール前の攻防で立て続けに、TMOもなしにレフリー個人の判断で、ノートライの判定になってことも、不信感に繋がってしまっている。
ただし、このレフリングはジャパンの方だけに不利な笛というわけでなない。オーストラリアAにも不利になる笛も同じくらいにあった。という意味で公平な一貫性のあるレフリングだったと言える。
しかし、この意外な判定に一瞬足が止まってしまったのがジャパンである。セルフジャッジと言うまではいかないが、そういったときに、ふと気が抜けたような間ができてしまうのがジャパン。一方そこでチャンスとばかりに集中力をあげるのが、オーストラリアAの選手達。
2023年のW杯、ニースでのイングランド戦のいわゆる「ヘディング」トライのときにジャパンの足が留まったことを思い出した。(この日もヘディングの判定もあった)
その差である。この差は大きい。
これがどこから生まれてくるのか?これは、長年培ってきた日本と欧州のラグビー文化の差なのかもしれない。つきつめれば、民族固有の文化的な差なのかもしれない。「闘争」や「動」の状態がカレントである欧州の文化と、「和」や「静」の状態がカレントな日本文化の差なのかもしれない。
また、ラグビーというスポーツにおけるレフリーの存在の意味合いの違いがあるのではなかろうか?日本ではレフリーは絶対なのだから、盲目的に従えと教えられる。そこで疑問な笛の判定に出会うと、選手の意識の中に、納得してプレーを続ければならないという「理性」と、納得できないという「感情」の間に隙間ができる。欧米ではレフリーへの過度なリスペクトの文化は薄いのでその問題は起こりにくい。
このような隙は、うまくいっているプレーでボールがこぼれれたりした場合やミスが起こった時の攻守の切り替え(=いわゆるトランジション)の際の遅れとして顕著に現れてしまう。ミスがおこっても、落胆している暇はない。このゲームでもボールが暴れてどちらにもピンチやチャンスが訪れる場面で、切り替えされ最後にはオーストラリアAのトライになったような場面何度かがあった。
2,セレクションゲームおける無意識のプレー選択
この日のジャパンXVはラインアウトで苦戦した。チャンスのゴール前ラインアウトでも2本も取られている。ラインアウトが不利ならばもう少し工夫して前で取るなどの選択をすべきなのに、同じ過ちを何度も繰り返した。
またオーストラリアにイエロー、レッドがでて、数的有利になり、回せばトライといいったチャンスを活かしきれない。
これは、このゲームの勝利や得点よりもジャパン入りを目指すアピールの場であるといいう意味合いが強かったあったことに起因している。当落選のチャンスを初めて与得られた選手なら、無意識にアピールしたいというプレーがでてしまうことは否めない。
その結果、合宿で習得した技術を見せようするあまりに、ラインアウトやモールにこだわったりしていまう。合宿では個人の技術アップはできたのだろうが、チームスキルになっていない。ゲームの時間、得点差、体力、モーメンタムなどの刻々とかわる状況で、結果をだすことがスキルである。技術はそのための道具でしかない。早々に不運な得点を奪われてしまい、ゲームに勝つことを忘れてしまって技術がスキルにまで至っていない。
結局この日ジャパンXVがあげた得点は、矢崎の個人技のトライGという7点のみだった。
無意識に自然と、見せようとするプレーや、得意なプレーに走ってしまったことが7点だけという得点終わってしまったことにつながっている。無理なトライを焦りインゴールドロップアプトになってしまったことも3回ほどあった。
3,ジャパン本体の課題?
一番めの問題のラグビー文化の差にかんしては、昨年のジャパンには確かにその問題がくすぶっていた。その点は今回のジャパンXVと同じように、経験の浅い状況とジャパンの定着をねらうという選手の状況があったとえいる。今年のジャパン本体はウェールズ戦、PNCで実践をかさね、その課題はかなり払拭できているといえる。ただし、根深い問題で完全に解決できるものではない。
さらにこの日のジャパンXVはタックルミスとラインアウト、ゴール前のディフェンスで苦労した。ジャパンXVの91回のタックルにミスが27回あった。タックルに行って外された件数は27回だが、タックルにも行けなかったケースがあと数回はある。一方、ジャパン本体のここ数試合のタックルの成功率は90%近くあり、昨年からは大きく改善している。しかしフィジー戦だけは成功率は落ちている。ワラビーズ、南ア、アイルランドにタックルはどの程度通用するのか?
ラインアウトに関してはジャパン本体では、ディアンズ中心のラインアウトではマイボールは確実に取れているし、相手ボールも奪うほどの戦力になっている。しかも今回2m級のホッキングスが加わるので安定するであろう。
一方、ゴールを背にしたディフェンスはこの夏のジャパンでも課題であり、また、この日のゲームでは改善されている様子がまるで見受けられなかった。これが、ジャパンの代表クラスのメンバーとの個人フィジカルや個人のスキルの問題もあるだろうが、改善されてきているかどうかも見定めたい
また、代表レベルの課題は、コンテストキックに対する対応やマイボールの確保の問題だが、オーストラリアAはキックをあまり使わずに抜けてしまったので参考にはならなかった。ただし、失点が多かったために、キックオフが多くなり中楠のキックオフにはキックオフからマイボールにする片鱗が何度が見て取れた。
この日のジャパンXvから23日のワラビーズ戦に引き上げる可能性のある選手はみあたらない。あえて言えば個人技でトライをあげた矢崎くらいであろう。
といったところ
25日のメンバーを予想すると
1.小林 2.江原 3.竹内 4.ホッキングス 5.ディアンズ 6.ガンター 7.下川 8.リーチ
9.藤原 10 李
11,長田、12,ローレンス 13,ライリー 14,石田 15,矢崎
16,佐藤 17,祝原 18,為房 19,コーネルセン 20,コストリー 21,福田 22,中野 23 松永(グリーン)
ということになると思われる。すでに2027年にむけてチームは固まりつつあると感じる。
顔ぶれをみると、この日のジャパンXvとの実力差はありありと見て取れる。しかし、昨年の今頃は卿のジャパンXVと同じくらいだった。経験を重ね、成長をしてきた結果なのだ。
まずは25日の国立ワラビーズ戦が楽しみだ。