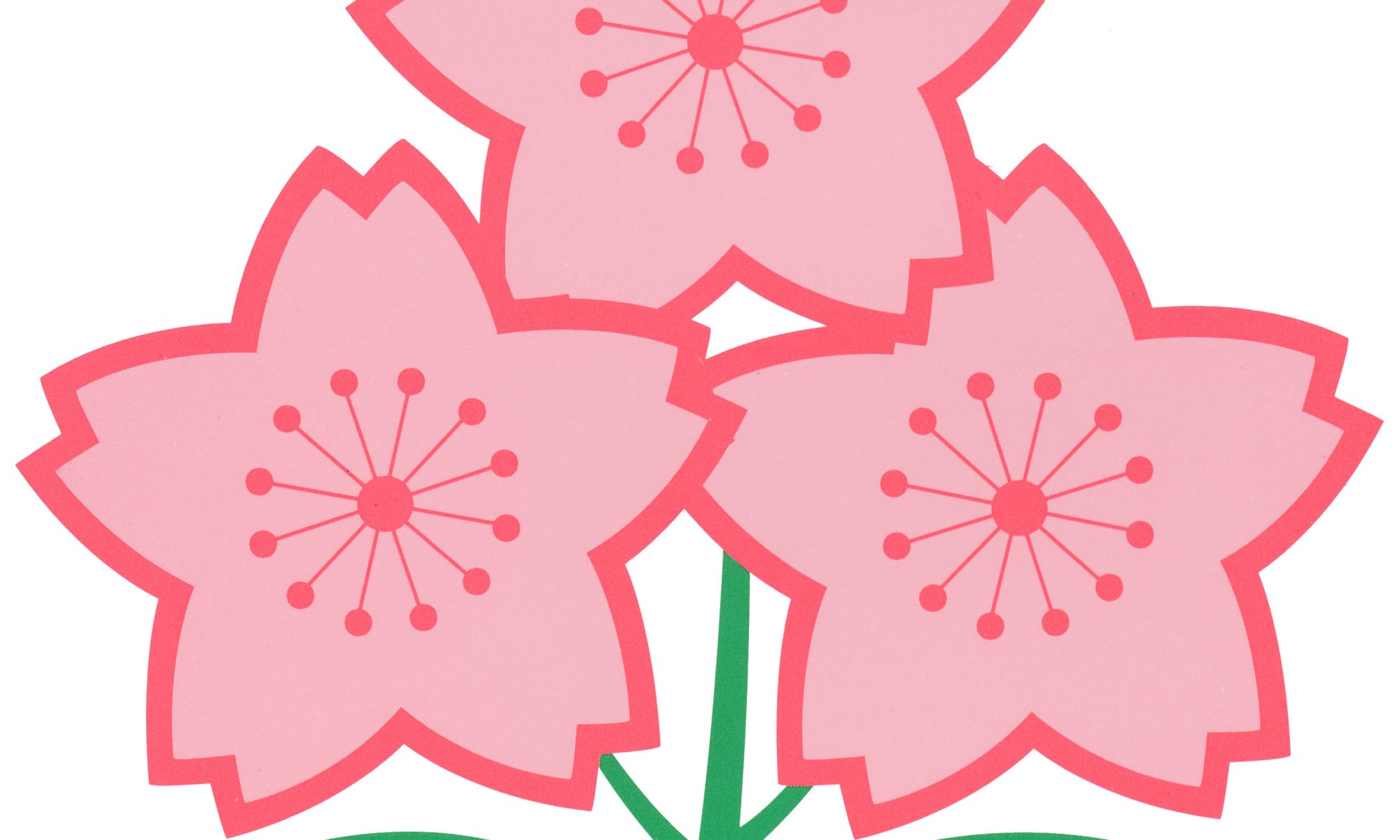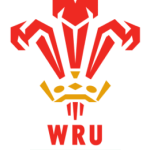後半の途中までは、ジャパンにはまったくいいところがなかった。
開始早々のアクシデントやアドバンテージの取り方、長いウォーターブレイク。
そして、ジャパンのペースになりかけるたびに、ことごとくぶつ切りになるレフリーの笛のタイミング。
それらが全て暑さに疲れ始めるウェールズを休ませる結果に繋がっていた。
中楠のシンビン。ペナルティトライの判断もあんなに長くTMOの時間をかけることはない。すぐにシンビンとペナルティトライの判断もできたはずだ。長いTMOの時間もウェールズを休ませることになった。見ている私もイライラさせられた、ジャパンの李舜臣にとっても同じ気持ちだっただろう。その心の乱れが、直後のキックオフのミスに繋がったと感じられた。
その上、このレフリーは、タッチの判断、アドバンテージのコールがありながら流す。反則があったか誤解させるような手の上げ方もさえもしでかす。
これらの笛に関しては、お粗末と言うしかないように思える。
しかし、レフリーも調子が良いときも悪いときもまる。選手や監督はそんなレフリングに心を見だされた時点ですでにゲームは負けである。
予想通りウェールズは戦前からLOの人材とラインナウト対策に苦しんでいた。その上開始早々のカーターの離脱というハプニングがあった。
ウェールズの前半の3つのトライのうち一つはペナルティトライであり、2つ目はその直後の李舜臣のキックオフミスからのセンタースクラムからの一人少ない左ライン際での独走トライであった。
この2つは普通なら防げたトライである。ジャパンがプレゼントしてしまったトライであるといって良い。その意味ではウェールズの得点力の低さは壊滅的状態であると言って良い。
しかも前半は、藤原の9番からの超速の代名詞である、速攻やコンテストのキックが全く出ていない。
この2つの要件がそろって、ウェールズは後半途中までギリギリで踏みとどまっていただけであったと言える。
前半からそれらが出ていれば、暑さに疲れるウェールズは糸が切れてしまいもう少し簡単にジャパンは勝てていた。
前半はエディジャパン史上「もっともスローな超速ラグビー」であったと言える。
後半の途中からジャパンに有利な笛が吹かれ始める。ノックオンのジャッジさえ明らかな吹き間違えも発生している。お粗末なレフリングだが、これがジャパンにモーメンタムを作り出した。
その上、後半は突如として藤原からのキックが多発されるようになる。コンテストキックだけでなく、普段ではキックしないようなタッチキックも藤原からのものになる。完全に作戦だったというよりはない。ただしこの変化は前半の「最もスローな超速ラグビー」が布石となってその効果は夏軍である。
こうなると、暑さに疲れの見えるウェールズはますますきつくなる。
スクラムでも笛は有利になる。
エディさんはこのモーメンタムを持続させるために、前三人を最後まで使い続けるというこの数年間のラグビーで全く目撃したことのない判断をした。この判断はスバラしい。
ここで1列目を変えてしまうと、せっかく有利に吹かれるようになってきたスクラムでの笛の基準をリセットしてしまいかねないからだ。
ラグビーのゲームには流れや波があるが、それを生みだすのも、止めるのもレフリーの笛次第であるということがあからさまになったゲームといえる。
そして、レフリーのレベルや癖を見極めて、その笛を味方に呼び込むつけるような役割こそ、9番や10番、キャプテンや、ヘッドコーチの重要な役目なのであるとうことも。
昨年はクレージーなほどに超速に猛進し、後半に息切れになったジャパンのスタイルからやっと脱皮してゲームの流れを活かすような、大人になりかけている。
ウェールズは、HC人材難でまだ決まっていない。キャプテンのモーガンがライオンズ遠征中で不在である。モーガンも遠く離れたオーストラリアの地でライオンズの中のたった一人のウェールズ人。気が気でないのではないだろうか、すぐにでも時差のない北半球に飛んできたいという気持ちであろう。
この日ジャパンの勝利は素晴らしいが、12日のゲームのほうがより重要になる。名実ともに格上になったジャパンは、格下のウェールズの挑戦を受ける立場になる。
負けてしまえば、ジャパンはせっかくの12位の座を受け渡し、14位に沈んでしまう。それがランキング計算の仕組みなのだ。
12日のレフリーは、実績のあるルークピアース氏が務める。
ブレイクダウンはコンテストさせるようするだろうし、些細な反則は流すようになり、無駄な笛はなくなり、ゲームはスムーズにストレスのないものになるだろう。
ジャパンは、このレフリングの変化を今度はどのように味方に引き寄せるのだろう。