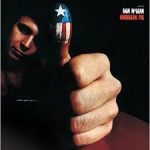ジャパンXV対マオリ・オールブラックス。考えてみれば、対象的な立場の者たちの顔合わせという奇妙で微妙な対戦ではあった。
一方は、ジャパンでのキャップを目指すという目標と意思をもち、そこに手がかかるかどうかという立場の者たちである。そして一方には、現時点ですでに今季のオールブラックスになることを逃した者たちが多く含まれる。
日本代表になるという価値と、オールブラックスになることの価値を比較できるのか?
日本代表を目指す者のマインドと、オールブラックスを逃した者たちのマインドの重みは比較できるのか?
オールブラックスとマオリ・オールブラックスの価値の比較に意味があるのか
ベクトルの幅は違っている。そしてその方向はすれ違う。したがってそんな比較は意味がない。
ただし、その一方にはひとつだけ間違いのない価値あるもの存在している。
それは「マオリであるということの矜持である」
オールブラックスの試合前のウォークライ「HAKA」は世界的に有名である。それはマオリの文化であり、存在そのものを象徴するものである。つまり、マオリオールブラックスの「HAKA」こそが正真正銘の本物の「HAKA」なのである。
6月28日、17:58分。満員の秩父の宮での「HAKA」はまさしく本物だった。
つまり何が言いたいかというと、オールブラックスにはないものが、マオリ・オールブラックスにあり、それは何にも代えがたいものであるとうこと。HAKAはその一つにすぎない。
彼らは極寒の南半球(気温4度)から、6月では異常な猛暑(気温34度)の東京にまで足を運んできた。8836Km。気温差30度。しかも2-3日前まで強烈な強度の優勝争いを終えたばかりで、この後すぐ、北島のマオリ縁の地ファンガレイに戻って、スコットランド代表戦を迎えねばならない。彼らは、どうしてこんな過酷なスケジュールを受け入れられるのか?
彼らにはどうしても取り戻したい忘れ物があったのだ。昨年7月13日の豊田スタジアム。やはり、猛暑と高い湿度の中のゲームだった。同じジャパンXVとの対戦。14−26の敗戦。忘れ物はマオリの「矜持」であった。この過酷な遠征はその「矜持」を取り戻すことにあった。
「ブライド」と「矜持」とは違う。ブライドは他と比較したイメージや地位などが根拠になっているのに対し、矜持は自分という存在や技術や実績にもとづいて自身の中に湧き上がってくるものである。
それがどれだけのものなのか日本人である私達には完全に理解することはできない。理解に近づくにはマオリの文化、歴史、ニュージーランドの日常、風土、気候、それらを十分に知ることが最低限の必要条件だろう。ただし、それでもマオリの血を引いているものでない限りは、無理なのだ。
マオリの血を引くものの「HAKA」。そらはまさしく本物の「HAKA」だった。
しかし、キックオフ後の彼らはまだ「忘れ物」を見つけられなかった。ハンドリングエラーを続け、スクラムでもたつき、ディフェンスの連携を忘れ、コンバージョンキックは外しまくる(そのなかの1本はタイムオーバーという情けないもの)。無くしたモノを必死に探し出そうしているようだ。手さぐりのようだった。なんとか隠し通そうとはするものの彼らの表情からは、疲労困憊の状況が伺われる。もうギリギリまで追い込まれていた。
ハーフタイムのロッカー室で何があったかが知るよしもない。私には後半始まっても前半同様の状態と見受けられた。
しかし、後半の途中で、どうも「忘れもの」は見つかったようだ。なにがきっかけだったのかわからない。無くしたものが見つかるのは探すのをやめたときなどだ。
はたしてその後のゲームは一方的になった。
対するJAPANXVのことはここでは言及しない。ただ言えるのは、ジャパンとしての「矜持」を持てるまでに、結果を積み上げていくことを期待したいというだけである。
追記:マオリ・オールブラックスという存在を認めるところに、ラグビー界の寛容さを感じる。でもこれが、「アングロサクソンライオンズ」や、「大和民族ブロッサムズ」なんてことになったらやっぱり許されないんだろうなとも思う。
追記:Jスポーツの中継の中での大さんがいい話をしていた。
数十年まえにNZへ行った際、現地の土産物屋でマオリをジャージを買い求めたところ、店員のおばさんが喜びのあまり涙をながしたということだ。当時の観光の日本人はだれもがオールブラックスのジャージを買って、マオリのジャージなど見向きもしないのに日本人にもマオリのジャージを買う人がいることに感動していた。とのことだ。
時は流れて、昨日の秩父宮にはマオリのジャージを着た日本人もちらほら見受けられたこともまた感慨深い。