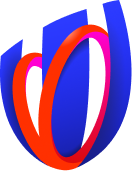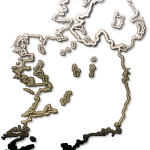こんなことを書くと格好をつけているだけのように思われるかもしれない。気取っているように思われるかもしれない。言い古されているかもしれない。そう思うと口にするのはちょっと気恥ずかしい。ベタなセリフだ。
でもあえて今、声を大きくしていいたい。
現に戦争状態にある国がある。その他の地域でもいがみ合いあっている。世界中で戦争の足跡が近づいてきていると感じる。
だからこそ言いたいのだ。言わねばならないのだ。
「ラグビーワールドカップは世界平和のためにある」と
なぜかといえば、それにはまずはラグビーの成り立ちから話を始めなければならない。
1,はじめに祝祭と言う名のフットボールありき
そもそも中世の大昔、フットボールは年に一度の祝祭のイベントだった。その日だけは街中が無礼講で大騒ぎをすることがゆるされた。数百人の男どもが街対街で一つの豚の膀胱で作ったボールを巡って大騒ぎをしたのだ。これが「原始フットボール」だ。村の坂道、林の中、橋の上、川の中でボールの争奪が繰り広がれた。相手の街の教会の扉にボールを付けた側が勝ちとなったり。反対の街の港の海にボールとともに飛び込んだら勝ちといった決め事があった。1点入ってしまえばそこで祭りは終了となる。しかしこんな楽しい馬鹿騒ぎを終わらせたくない。そこで、ボールは足で蹴ることにしょうとか、ボールを前になげるのはやめようといった、ゲームを長引かせるルールが採用になった。そんな中、あるこすからい者がゴール前のPUBで飲んで酔っ払っているふりをし待ち構えていて、ボールをひろってゴールなんで終わり方になることがあった。これは流石にずるいだろうといことになる。そこからオフサイドのルールも発展した。
もちろん終わったあとには敵味方ない祝宴が待っている。
そしてそれは普段領主や国王に対する不満もあるので、それらの不満もぶちまける恣意行為の場にもなった。大騒ぎでけが人もでる。為政者はしばしば「フットボール禁止令」を発布した。それでも村人たちはフットボールをやめなかった。
時代は下り近代になり、フットボールがイングランドのパブリックスクールの学校のグランドでおこなわれるようになる。当時の校内は今と同じいじめ問題などで揉めていた中、丈夫な体を作ったり、健全な精神力を鍛えるための教育(「筋肉的キリスト教」)の一環だった。学校ごとに校内だけ通用する独自のルールを作りクラス対抗がおこなわる。時をまたずそれは他の街の学校との対戦となる。今回はどちらの学校のルールでやるのかから交渉が始まる。いちばん面白かったのが、ちょうど200年前エリス少年が走り出したことでできたラグビー校がきめたルールであったので、そのルールが広がり、ラグビー高校式フットボールが成立する。これがいまラグビーと言われるスポーツの誕生だ。そして、各地のパブリックスクールのOBたちがクラブを作り街単位のゲームが行われるようになる。学校同士、街と街の交流が定期戦を通して何年も世紀を超えても続いている。
それはビクトリア女王の時代であった。その時のイングランドは世界中に植民地をもっていた。そしてそこに赴任した軍人や役人、民間人もそんなラグビーで楽しんだ。楽しそうな様子を見た現地の先住民も見様見まねで始めた。一緒になってチームを組んで夢中でプレーした地域もあれば、完全に白人だけ、現地人だけというチームを編成した地域もあった。本国から一個師団が寄港した際には本国のチームに対抗して、メルボルンやオークランドの赴任地のチームが奮闘した。そこには本国に負けるかという意地があった。ゲームが終わればお互いにわかりあえて、そのことで本国と遠くは離れた赴任地との距離は縮むのだった。
そのようにお互いわかりあえて、友好関係を築き、それを継続させるためにラグビーが存在した。しかし、その裏にはローマ時代にはあまりいい言葉ではないが、「パンとサーカス」という言葉があったように、原始フットボール時代からもラグビーがサーカスの役目であったということも言える。民衆の不満や不平のはけ口でもあったのだ。有り余った若者たちのエネルギーの発散の場であった。そんな発散の場がないとそのエネルギーは暴動や一揆に発展してしまう。
国内でもスコットランドやウェールズ、アイルランドもイングランドに挑戦状を叩きつけた。もちろん戦争ではない。ラグビーで対抗するのだ。そしてゲームが終われは一緒に敵味方なくグラスを傾け祝杯をあげるのだ。
「戦争の代替物としての役割」
でもまあそれでも良いではないか、いがみ合って暴力沙汰になり、それから紛争や戦争になるよりも代表の15人同士が安全な?ルールの元戦うことで、それらが避けられるのだから。
(実際にフランス対イングランドの100年戦争のさなかに、ブルターニュのあるところでブロア軍30(フランス傭兵軍)人とモンフォール軍(イングランド代表)の30人(ラグビーの倍の人数)が、樫の木の下にあつまり、代理で戦いを行ったこともある。それが「30人の戦い」。ここでは長くなるので紹介だけに留める、詳しくはここをクリック}
2,それではなぜラグビーでお互いわかり会えるのか
そこで一つの疑問がでてくる。
「なぜラグビーをするとお互いの距離が短くなり、仲良く慣れるのか」
まず、喧嘩のあとで友好が深まるという題材は、様々な映画の主題になっている。
ジョン・フォード監督の「静かなる男」では、アイルランドが舞台だった。元ボクサーのジョン・ウェインが主人公。生まれた村に帰ってきて見初めた美女(モーリンオハラ)にプロポーズをするが、その兄の猛反対と妨害行動にあう。一方的な暴力や嫌がらせに耐えに耐えるのは、ボクシングの試合の最中に死亡事故をおこしてしまったからだ。しかし最後はその禁をといて、ついに殴り合う。そして仲良くなってめでたし、めでたしめでたし。という映画だった
宮崎駿の「紅の豚」では、イタリアのアドリア海が舞台だった。
主人公ポルコと粗雑だが憎めないアメリカ人カーチスが、航空技師の少女フィオと借金のかたとホテルアドリアーノの女主人ジーナを巡ってお互いの飛行艇で空中戦を行う。空中戦は引き分けにおわるが、そのあと浅瀬にて素手の殴り合いになる。最後は、ジーナの仲裁とイタリア軍の到来の情報で、両者痛み分けとなる。二人はわかり合いカーチスはジーナとフィオを諦める。殴り合いの最中ポルコは一瞬人間に戻るがカーチスはそれも見逃さななかった。(「ラピュタ」でもウェールズの炭鉱が舞台の場面で似たような設定がある)
けんかのあとで仲が深まるのはよくあることだ。お互いに無視しあって避けていて仮面を被っていればいがみ合いがずっと続く。本心をさらけ出してぶつかることも必要である。けんかにもルールがある。倫理がある。素手でなくてはならないのだ。ラグビーにもそれなりの規定があるが、その前に「闘争の倫理」が存在する。おたがい激しくぶつかり合っても、生身の人間同士であることが前提だ。
ラグビーという激しいスポーツのあとに仲が深まるのは当然である。ラグビーはそれこそ全人格(知性、体力、マインドなど)すべてをさらけ出して戦うスポーツだからだ。その全力を足したもの同士、いいところも悪いところもお互いを知ることができる。分かり合うことができる。
ラグビーであんなに激しい戦いをしたのに、「ノーサイド精神」で終了後はなんであんなに仲良くできるのだろうという疑問もあるかもしれないが、お互いをたたえある気持ちに微塵の嘘はない。
そこには「オキシトシン」というホルモンの作用もある。「愛情ホルモン」とも「幸せホルモン」言われる。お産のときの痛みを柔げる作用があり、旧来は女性に特有のものと思われていたが、男性にも存在することがわかってきた。このホルモンの効果はで優しい気持ちになり、共感を持ちやすくなり、心を安定させ、痛みも和らげる。体と体のふれあいや、一緒に過ごした時間の中でこのホルモンは分泌される。
15人が味方同士と相手の15人とも全員が肌を触れ合って、すべてをさらけ出して、力比べをするスポーツなど他にない。人間の生理学上でもラグビーが友好の手段であることは証明されているといえる。
ラグビーを一度でもプレーしたことのある者どうしは、初対面でもすぐにわかり会える。あの痛み、苦しさ、そして歓喜と連帯感、爽快感、友情、そんな体験をしたもの同士。そこに言葉はいらない。嘘はない。信頼できる者である、仲間であるいうという直感が意識下の何かから、お互いの表情に行動に命令が下る。もう5分後には次の飲み会の打ち合わせが始まる。
「オキシトシン」は一緒に飲食をしたり、声を上げたり、歌ったり、共同作業をすることでも分泌される。サポーター同士が敵味方なくビールを飲み交わすことで、一体になれるのは「オキシトシン」のおかげだ。ラグビーがあることで、全員に幸せは訪れる。
3,そして今ワールドカップがある
ワールドカップではそんなラグビーをめぐって、全世界から人が集まる。選手やチームだけなく、ファンやサポーターの数は数十万人になる。お互いに触れ合うことでわかり会える。いやわかり会えなくてもわかり合おうとする気持ちが大切だ。わかり合おうとするためのマシーンがラグビーであり、ワールドカップである。ワールドカップに参加するサポーターは自動的におたがいにわかり合おうとするように仕向けられる。それが2ヶ月間にもわたって繰り広げられる。
われわれはまず、開催国のフランスのことを知ることができる。われわれはフランスのことをどれだけ知っているであろうか。70年初頭までフランスは日本でもあこがれのお手本の国だった。それがいつしかある時までアメリカ一辺倒になってしまってはいなかっただろうか。
「パリ?」」「シャンゼリゼ?」「エッフェル塔?」。それでは日本のことを「さむらい」「芸者」「富士の山」くらいしかわかっていないぼんくら外国j人と同じだ。
今回、トゥールーズやマルセイユ、ナントという街の名前を初めて覚えたなら、それが、第一歩だ。フランスは広いし奥深い。パリだけではない。地方には地方の文化があり、特徴がある。
そしたら今度は、フランスの文化、歴史、風土や人間性に触れてみるべきだ。フランスの歴史を知れば知るほど、それはものすごく面白い。いい面もあり、はずべき悪い歴史もある。ワインやグルメでもいい。宗教や、革命や人権、思想や哲学にまで興味は尽きない。
そして、次には日本の対戦相手の国やその他の参加国のことを知ることができる。ゲーム前に歌われる国歌や地域のアンセムにはその国や地域の歴史や思いが濃縮されている。意味を知るだけでも十分だ。一緒に歌えばもう一瞬で仲間になれる。
91年の戦いではじめて、「フラワーズオブスコットランド」と「スイングロウ」を覚えた。2015年の大会では、南アフリカ戦のあとでも、「ショショローザ」で助かったし、2019年には、ウェールズの爺さんが「ブレッドオブヘブン」を突然3度上でハモッてきたには驚いた。花園ではジョージア国歌タヴィスレバのお陰でジョージアの美人姉妹といっしょに写真に収まることができた。
そういえば2019年の前回日本大会のときの初戦はロシアだった。日本は開幕戦でそのロシアに苦しめられたのだが、ゲーム後にそんなロシア人サポーターとも仲良くなれた。彼らはソユーズかスプートニクの宇宙飛行士の仮装をしていた。彼らとは数日後、熊谷のサモア戦で再会することができた。言葉は通じなかったが、ビールで乾杯し一緒に写真におさまった。わかりあえた様に思えた。その時はまだ戦争なんてなかった。ウクライナとの戦争になっている今回はロシアと彼らの参加は叶わなかった。彼らも戦争の犠牲者である。
日本の初戦のあいて、チリについて知りたいと思い始めれば、それも世界平和の第一歩である。日本にとてチリはワインだけではない。チリにも国の歴史がある。革命がある。彼らの思いがある。歌がある。このサイトではここで特集を組んだ。(ココを参照ください。)
アルゼンチンについてはどうか、イングランドについてはどうか、サモアはどうなのか。フランスの現場に行けばサポーター同士のでもふれあいができる。言葉が通じなくてもラグビーの素晴らしさを語り合うことができる。現場に行くことにはそれだけのものすごく大きな価値がある。それはお金ではけっして買うことができない。
TVの前でもチリのことアルゼンチンのこと、サモアのことなどをすこしでも学ぼうではないか。わかりたいと思おうではないか。
ワールドカップは対戦国だけなく、ジョージアや、ルーマニア、ウルグアイ、ナミビアなどふだんあまり馴染みのない国についても知るための一歩の絶好の機会だ。ぜひともそんな国にも思いをはせてもらいたい。興味をもつことが世界を知ることになり、それが友好につながり、ひいては世界平和になるのである。
仕事や上司や学校、子育てや介護、自分たちだけでも毎日悩みや精一杯の生活かもしれない。そんな余裕などがないかもしれない。
そしてひとりひとりの力は小さいかもしれない。
でもこのワールドカップの機会に少しつづでも世界に目をむけようではないか。お互いにわかり合おうとすることが、世界の平和につながるのだ。
だからこそ言いたい
「ラグビーワールカップは世界平和のためにある」のである。
気恥ずかしいがそれでも言いたい
「ラグビーワールカップは世界平和のためにある」と