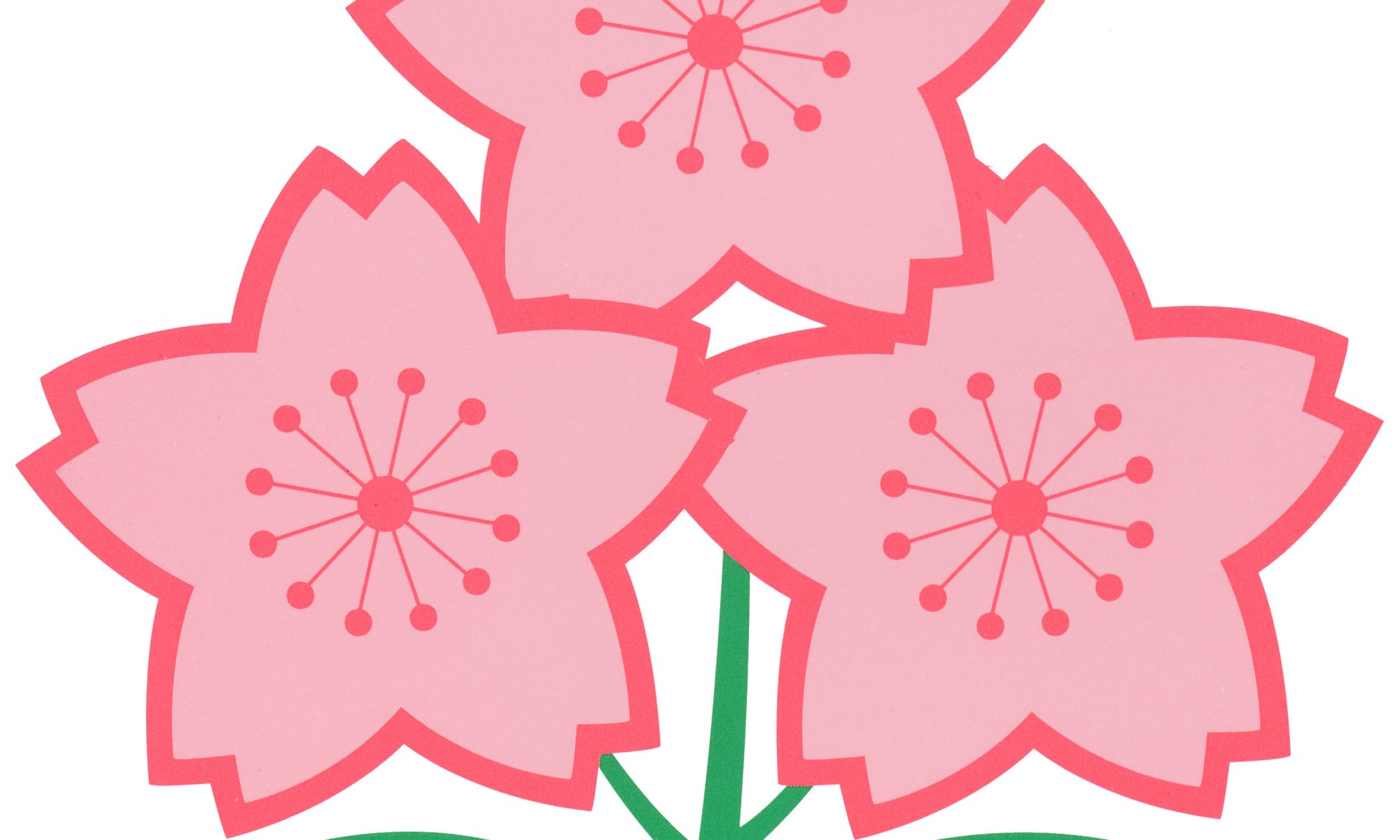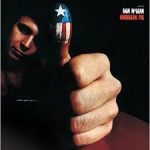1,第一列
1. Angus Bell (44 Tests) – #940; Hunters Hill Rugby Club
2. Josh Nasser (8 Tests) – #979; Easts Rugby (Brisbane)
3. Zane Nonggorr (16 Tests) – #966; Gold Coast Eagles
16. Billy Pollard (16 Tests) – #958; Lindfield Junior Rugby
17. Aidan Ross* – uncapped; Bond University
18. Tom Robertson (36 Tests) – #898; Dubbo Kangaroos
長く先発を貼っていたレジェンドのJスリッパーが10月4日のNZ戦で151Cを得て引退。1番の座はしばらくは今回先発するアンガスベルが務めることになる。アンガスベルは2023W杯にも出場して経験も豊富。ルーズヘッドの2番手にはトムロバートソンがいるが今回はお休み。今回控えに入ったのはエイダンロスで現在29歳だが、トップリーグの神戸製鋼にいたこともあり、オールブラックスキャップ1を持っている。今回3年居住がみとめられて、ワラビーズの一員になった。出れば初キャップとなる。
フッカーは1番手のBポラードは今回は控えからの参加となる。2番手の座をポレッキーとアモサ、ナッソーが2番手を争っているが、今回はそのナッソーが先発。
ナッソーは2024年にデビューして2年目で8キャップ、先発は今回が初めてでは無いだろうか、10月4日のNZ戦でも控えからの出場だった。
タイトヘッドは、31歳85Cのアラアラトア、29歳C65で148Kgトゥポウがファーストチョイスだが、今回は両人とも休養である。若手のノンゴールが先発で、ベテランのトムロバートソンが控えである。
スクラムでは先発のアンガスベル192cm、ナッソー192cmノンゴール189cmでジャパン172cmの江良)との高さを合わせるのは難しいと考えられる。ジャパンは低いスクラムで対抗する。
レフリーのベン・オキーフ裁きはどの程度なのか、それにどう対応できるのかがスクラムの勝敗を左右するだろう。彼がジャパンに高さを合わせるように指導すれば組みにくくなる。NZ出身のベンオキーフのレフリングにはオーストラリアの選手は馴染みが深いのでコミュニケーション部分でオーストラリアが有利に組むことになるかもしれない。
2、ロック陣
4. Jeremy Williams (20 Tests) – #973; Wahroonga Tigers
5. Lukhan Salakaia-Loto (43 Tests) – #914; Randwick
19. Josh Canham (1 Test) – #987; Harlequin Rugby Club
ロック陣は、ファーストチョイスはNフロストとスケルトンのコンビであろうが,今回はこの2人はお休みである。今回はいつもは控えからの出場が多い、198cmのジェレミーウィリアムス201cmとサラカイアロトのコンビが努め、控えには先週ジャパンXVをラインアウトで苦しめた202cmジョシュキャナハムが入る
スケルトンが出れば140kmと重さもあり、スクラムも核になるので脅威だったが、サラカイアロトも130kあるのでスクラムの重さは依然脅威ではある。
そして、ジャパンは戦力の一つであるラインアウトで苦戦することになると予想される。
3,第三列
6. Nick Champion de Crespigny (c) (2 Tests) – #991; Canberra Grammar School
7. Carlo Tizzano (11 Tests) – #982; University of Western Australia
8. Rob Valetini (57 Tests) – #929; Harlequin Rugby Club
20. Harry Wilson (31Tests) – #933; Gunnedah Red Devils
このところ先発の常連であった、Tフーパー、マクライトの2名を温存して、
いつもは控えのチザーノに加え、ライオンズ戦でデビューし、まだやっとキャップ2のクレスペグニーをキャプテンをして抜擢し先発させる。したがって、キャプテンとして高い評価を得ているハリー・ウィルソンは控えからの登場となる。何を想定しているのかシュミット監督のこの意図はわかりかねる。かわりのナンバー8にはアグレッシブなバレティニがはいる。ジャパンにとってはこのバレティニのがむしゃらな突破力には注意しなければならない。
4,ハーフ陣
9. Jake Gordon (32 Tests) – #925; Canterbury Juniors
21. Ryan Lonergan (2 Tests) – #933; Tuggeranong Vikings
10. Tane Edmed (4 Tests) – #990; West Harbour Juniors
ハーフ陣には怪我が多い。この夏には一度引退したニックホワイトを呼び戻さねばならないくらいだった。そして話題のリーグラグビーから戻ったカーターゴードンはメンバーに入っていない。今回は10月4日のAB戦と同様、怪我から復帰したベテランのジェイクゴートンと、エドメドのコンビとなる。エドメドはこの夏チャンピオンシップの南ア戦で控えに入って、アルゼンチン戦、NZ戦で先発している。
控えのSHには若手で今年のブレディスロー杯でデビューしたばかりのロネガンが入った。
SOにはもうベテランの域にはいったかつての悪ガキJオコナーが復帰しているが、今回は欧州クラブの事情で来日していない。ロレシオも同様である。
5,センター陣
本来のワラビーズのセンターといえば、おなじみのイキタウとリーグラグビーから加入しイスラエルフォラウの再来とのスワーリの2人なのだが、この2人は出ていない。キャンピオンシップで活躍したスワーリのダイナミックなプレーを見てみたかった。
今回はかわりにパイサミと、若手のフロックのコンビである。そして先週ジャパンXV戦に出ていたハミッシュスチワートが控えに入る。
12. Hunter Paisami (32 Tests) – #932; Harlequin Rugby Club
13. Josh Flook (5 Tests) – #972; Brothers Rugby
22. Hamish Stewart (2 Tests) – #986; Toowoomba Bears
6,バック3
11. Dylan Pietsch (7 Tests) – #978; Leeton Phantoms
14. Corey Toole (4 Tests) – #992; Wagga Waratahs
15. Andrew Kellaway (45 Tests) – #943; Hunters Hill Rugby Club
23. Filipo Daugunu (15 Tests) – #931, Wests Bulldogs
FBのベテランケラウェイが脅威である。ケラウェイは昔NECでもプレイしていた。キック処理も安定している。
しかし、トライゲッターの大スターとなったヨーゲンセン、最近売出中のハリーポッター(本名)は今回出てこない。
今回の11、ピーチ14、トゥールの両翼とも経験の浅い選手である。ピーチはセブンスはセブンスの出身で今季のチャンピオンシップでデビューしたばかり。
控えにはフィジー出身のダウングヌが入っている。
7,ワラビーズ戦の戦い方
ワラビーズは今回のジャパン戦には主要選手の多くは出ていない。このあとイングランド戦など欧州遠征が控えており、そこで、27年W杯の選手層を厚くするのが目的だからである。ジャパン戦はその前哨戦と位置づけ、チャンピオンシップでの出番の少なかった選手を中心に選出されている。ワラビーズにジャパンXVでの大勝のイメージがあるとすれば、間違いである。ジャパンXVと本来のジャパンの実力、経験の差は非常にある。ジャパンは初めてワラビーズから勝利を掴む期待は高まる。
ワラビーズといえば、相手を分析し理にかなった組織的なアタックを見せるイメージがあるが、また序盤リードされても粘り強く戦い、次第に流れを掴み最後には接戦や逆転に持ち込むゲームメイクの強かさも兼ね備えている。
そして、このところのワラビーズは9シェイプや10シェイプからボールを下げずにワンパスでFWを縦をつきディフェンスの突破をはかる戦法が有効に働いている。これで、南アやアルゼンチンを破っている。
ジャパンはこれを受けてしまわず前に出てダブルタックルで止めなければならないが、ある程度は食い込まれることは覚悟しなければならない。ここで反則せずに守れたにしても、オーストラリアA戦のように、何度かのアタックでゴール前まで責めれらてしまうと、トライの量産に繋がりかねない。
しかもときよりワンタッチでの外への早いパス回しも見せるので、中央部分のみのディフェンスに集中してもいられない。
確実に少しでも前で止めることで、連続攻撃を寸断することが必要だ。
ジャパンの弱点はコンテストキックの処理であるが、幸いなことにワラビーズはキックをあまり多用してこない。しかし、もしもハイパントを上げてくるなると、ワラビーズのバック3の身長はいずれも185から190あるので、ジャパンは苦しくなる。
スクラムは非常に重いトゥポウやスケルトンが抜けた分、対等に組めると思われるが、前述したように高さの差が気になる。ラインアウトは苦戦するかと思われる。
キックでエリアマネジメントを確実に行い、自陣深くに攻め込ませないようにし、失トライを3トライ以内に抑えられれば、勝つチャンスは大いにあるといえる。
ジャパンは、矢崎、ライリーのスピードを活かしてか、または、PGからの藤原、竹内らの早い仕掛けが決まれば、少なくとも3トライは取れるのではないだろうか?ディアンズのチャージなどでの攻守の切り替えにイーブンボールで素早いサポートをできるのかも見どころである。
ワラビーズの縦攻撃を寸断できれば、ワラビーズは外へボールを回す戦法に切り替えるタイミングがある、その時、ライリーや長田がインターセプトを狙うのも悪くない。
最後までもつれる好ゲームとなるのは間違いがない。