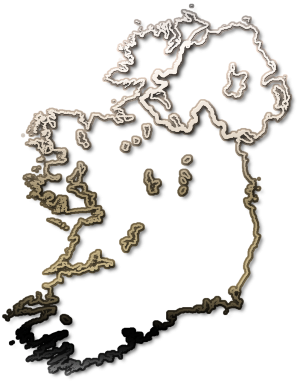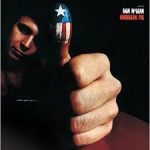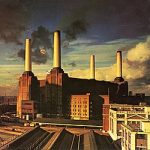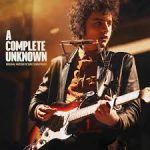1,はじめに
この曲はアイルランドに伝わる有名なトラッドソングであり、様々なアーチストが取り上げている。ただ、海外のラブソングなどによくあることだが、女性が歌っているものには、Sheを Heに変えて 「He moved thru’ the fair」としているものもある。しかし、Sheでないと意味が伝わらないのだ、それを明らかにしていきたい。まずはケルティクウーマンの美しい歌声をどうぞ。
2.歌詞と訳詞
1,My young love said to me, "My mother won't mind
And my father won't slight you for your lack of kind."
Then she stepped away from me and this she did say:
"It will not be long, love, till our wedding day."
私の愛する人はこう言った「母さんは気にしない
父さんだって仏頂面は気にしない」
彼女は去っていき言った
「結婚式までもうすぐだわ」
2.She stepped away from me and she moved thru' the fair
And fondly I watched her move here and move there
And she made her way homeward with one star awake
As swan in the evening moves over the lake
彼女は私から離れて、市場の中を歩き回った
彼女があちこちと見て回るのを見てた
彼女は一番星とともに家路についた
夕暮れの白鳥が湖の上を飛ぶように
3.The people were saying,No two e'er were wed
But one had a sorrow That never was said.
And I smiled as she passed With her goods and her gear,
And that was the last That I saw of my dear
片一方が話せないほどの悲しみを背負っていれば
二人は結婚できないと人は言う
私は彼女が嫁入り道具を持って歩くのには微笑んだが
それが彼女を見た最後だった
4.I dreamed last night that my young love came in
He came in so sweetly, her feet made no din;
He stepped close beside me, and this he did say
'It will not be long love, till our wedding day'
昨夜、恋人がやって来る夢を見た。
彼女はとても優しく、足音も立てずに入ってきた。
彼女は私のすぐそばに来て、こう言った。
「私たちの結婚式の日まで、この愛は続かないわ」
「私たちの結婚式の日まで、この愛は続かないわ」
(訳詞は筆者)
一見して結婚式を間近にした幸せなカップルの歌かと思いきや、曲の最後に花嫁は幽霊となって夢枕に合われるという展開にぎょっとする。なぜこんな悲劇的展開になってしまうのだろう。
3,「ブレホン法」と映画「静かなる男」
実はこれには、アイルランドに伝わる古い習が関係している。それがまだアイルランドの田舎には残っているらしい。その名残がこんな悲劇を生んでしまったのだ。
アイルランドの生活習慣には「ブレホン法」の影響がある。これは、アイルランドに聖パトリックがキリスト教を広める前の古代のケルト時代あった法典である。この古代からの法典では、現代のように女性の権利が非常に進んだものだった。例えば、女性の出世などもみとめらているし、財産権なども認められていた。それがかえって皮肉な結果を生むことになる。実はその影響からか、結婚にあたっては男女は対等であり、花嫁は持参金や嫁入り道具を用意することが重要な条件だと思い込むことになるのだ。
1952年のジョン・フォード監督映画『静かなる男』は世界的に最も有名なアイルランドの映画といってよい。
 その映画にモーリンオハラのこんな台詞もあったのを覚えておいでだろう。
その映画にモーリンオハラのこんな台詞もあったのを覚えておいでだろう。
「こちらにはピアノ、こちらには食器棚、私の気に入りの持ち物の家具にかっこまれた生活がしたかったのよ
洗濯もするし、炊事もするわ
でも持参金を取り戻すまでは対等な夫婦ではではない。
だからそれまでベットは共にしない」
この映画でなぜああにもヒロイン役のモーリンオハラが持参金にこだわるのかを不思議に思った方も多いことだろう。それが上記のアイルランドの風習なのだ。この映画では、アイルランドの花嫁にとっては持参金があることが、対等な夫婦になる条件としてとても重要な事項だということがプロットになっている。つまり、「玉の輿」の結婚は適齢期の女性にとってとっても恥いることなのだ。・
4,lack of kindなのか lack of Kine なのか
1番の歌詞の「lack of kind」のところも単純には「親切さにかける」と訳せるのだが、聞き様によってはlack of Kineとも聞こえてしまう。lack of Kineとはっきり歌ってるものもある。これでは、「lack of Kine=雄牛がない=貧乏である。」という意味になるのだ。
彼の両親が彼女の家が貧乏なのを分かってくれていて、持参金などなくても気にしないといってくれているのならまだしも救いがある。が、もしかして、少し前に花嫁は花婿の両親には思い切って、「lack of Kine(私は財産はありません)」とおずおずと打ち開けたのかもしれない。しかし、ノーテンキで裕福な花婿の父親にはその仕草などから「lack of kind(親切さにかける)」と聞こえてしまっているという可能性がある。そうだとしたら、それを今更否定できない花嫁となり、より悲しくなる。貧乏で嫁入道具が揃えらなく悩んでいるのも誰にも言えなくなってしまっているのだ。精神的に追い詰められている様子が伺われる。
3番の歌詞にあるように、「片一方が人に言えない悲しみを背負っていれば幸せな結婚はできない」のだ
5,Fairのもつ様々な意味
ここで、Fairという言葉の複合的な意味が重要になってくる。一つは「市場」、もう一つが「祭り」、最後が、「公正」である。3つの意味が込められている。
1)Fair=市場
市場ではさまざまざな家具が売られている。花嫁のほうは市場で嫁入り道具の家具などを憧れながら見て回っているが、貧乏なので十分に揃えることができない。きっと持っている少ないお金だけで、どうやったら恥ずかしくないだけの家具が揃えられるのかを悩みながら、市場を回っているとかと思うと2番の歌詞からとても切なくなる。
2)Fair=お祭り
アイルランドの結婚式の定番として、大勢が集まる市場やお祭りの中で2人だけがいつの間にいなくなるとう演出がある。しかし、花嫁は一人だけで花婿の前から居なくなった。これは不吉であり、その後の悲惨な行動をうかがわせる。しかも「夕暮れの白鳥が湖の上を飛ぶように」だがら、美しくも悲しさに溢れている。
3)Fair=公正さ
二人は愛し合っていても自分の家が貧乏なのを隠し通して、結婚式の日取りの近くまで来てしまった。嘘をついていた訳ではないが、公正さ誠実さにかけている、この精神的重圧が、彼女にのしかかってくる。そしてそれは結婚式の日が近づけば近づくど、重くのしかかってくる。
5,LONGの2つの意味
2番と曲の最後に出てく「’It will not be long ,love till our wedding day.」の文節。
これも文節の切り方で違った意味になってくる。
「’It will not be long ,love till our wedding day.’」とすれば
「愛する人よ、結婚式までもうすぐね」
となる。単純に考えれば、結婚式を待ちわびる幸せな花嫁と解釈できてしまうが、そうではない。結婚式がどんどん迫ってきても持参金や嫁入道具が揃わないという。精神的に追い詰められてく状況なのだ。最初に出てくるこの歌詞の意味はこのとおるなのだろう
3番で全く同じ歌詞がでてくるのだが、
「’It will not be long love till our wedding day.’」とすると、
「私達の愛は結婚式まで続かない」という意味になる。
これは最後に、幽霊になって花婿の夢枕に現れた花嫁が、うらめしげにささやく言葉である。そう思うと背筋に寒気がはしる。夢の中に出てくる時点で、花嫁は自らもう命を断っているので、2人の関係は続かかかったのだ。
このまでくれば分かる通りこの曲は市場を歩き回るのが花嫁であることで意味が深くなる曲である。男性が歌えばSheのままであるが、何人かのアイルランドの女性歌手は、SheをHeに変えてHe moved thru’ the fair」と歌っているものがある。シニードオコーナーなどがそうである。シニードオコーナーは後になってShe moved thru’ the fairにすればよかったと後悔していたというとだ。