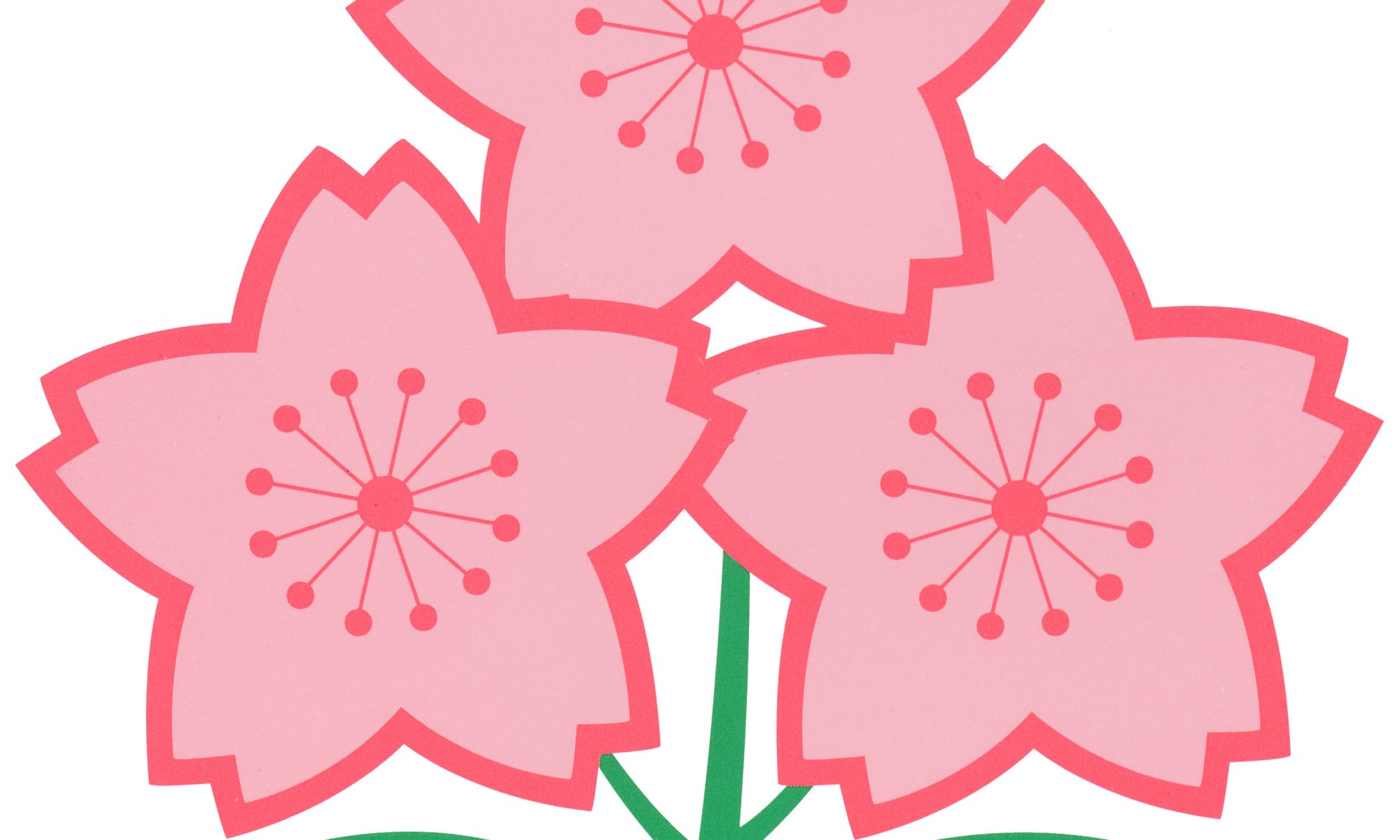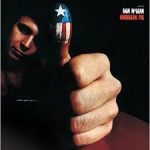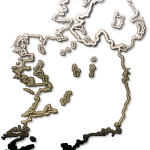屋根を閉めた蒸し風呂状態のゲーム。ハンドリングのエラーなどは双方ともおこる。不用意なディフェンスのミスや反則も双方に起こる。コンテストキックの取り合いからこぼれたボールがどちらにも有利に転がる。
こてはどちらが勝っても不思議ではないゲームだった。あと5分時間があればジャパンが2試合連続の逆転勝ちをできたとおもわれる。
そこで5日の対戦と12日の対戦の同じところ違ったところを取り上げてみた。またジャパンとウェールズの対応の違いも考えてみた。
第一の違い セットプレー
先週との違いの1つ目は前回はジャパンがわずかに上回っていたスクラム。圧倒していたラインアウトが12日にはほぼ互角になった点である。
スクラムに関してはウェールズが修正してきたというより、レフリングの差であると感じた。ルークピアーズさんのレフリングは一貫性があり、ウェールズは一貫してそれに順応したスクラムを組んでいた。先週のレフリーはウェールズにとってはレフリングにストレスを感じるレフリングだった。
ラインアウトに関しては、先週は開始直後4番が急遽変わってしまい、ウェールズには微妙なずれがあった。それにディアンズやコストリーのコンテストで、ウェールズのラインアウトを乱すことに成功した。今回はウェールズが本職のLOを入れ準備をしてきた分だけわずかに精度は上がった。(スローイングのミスなどはあったが)。ジャパンは相手ボールの時コンテストしてこなかった。これはあいてのモール攻撃にたいする作戦だったのかもしれない。しかしもう少し競っていれば乱すことが可能だったのではないか
第二の違い キックとその処理
二番目はキックの使い方と処理の違いである
今回は暑さの問題やハンドリングの問題から、双方とも序盤からキックをうまく使っている。違っているのはジャパンは先発の斉藤9番からのキックが多かったことである。前回は序盤での藤原からのボックスキックは殆どなかった。これも選手のスタミナを考えての作戦だった思われるが、キックの処理は若干ウェールズのほうが長けていた。とくに15番のブレアマレイは安定感がああった。
第三の違い 選手起用と交代の戦略性の違い
三番目は選手起用および、選手交代のタイミングである。
ジャパンの選手起用、交代と、ウェールズの選手起用、交代は全く正反対であった。その点でジャパンの方が作に溺れたというか考え過ぎだったのではないか。
ジャパンは勝った前回からは選手は怪我などの場合をのあまり変えたくはなかった、しかし、SHには斉藤をいれた。斉藤の導入は速さやコンビネーションというより、ゲームを作るという役目だったはずだ。その通りにキックを多く使った。その結果は前述したとおりである。選手交代のタイミングも、第一列のそう取っ替えも想定して考えていた作戦であり、それもうまくはまり、前半終了まえのトライに繋がった、
ウェールズの先発は負けた前回から変えたかったはずだが、人材がいない、しかもファレタウやコリーなど、試合にでられなくて、自動的にかわりの選手がでてきた。唯一の戦略的な面はSOの変更であった。選手交代のタイミングも、けが人や体力の限界で選手交代も対処的であり、最後はSHの選手をWTBとして投入せざるをえなかった。
詰まるところ、ジャパンの先発は作戦ありきであった。選手交代のタイミングも絶妙であった。ウェールズの選手起用と交代はほぼ受動的であり、戦略性を持っていたとはいえない。ただし、変わった選手はそれなりに無難に活躍した。結一の若手SOの抜擢は賭けでもあったが、それは成功したと言って良い。
第四の違い ディフェンス遂行能力
Jスポーツの解説の藤井氏は、ウェールズのマークするべき選手ははっきりと15番のBマレイだと断言していた。ということはジャパンの首脳陣もその分析は共有されていて、その対策も落としこまれているはずである。しかし、蓋を開けてみると、マレイにはかなり自由に走られてしまっている。それは遂行能力がたりなかったためと思われる。
また、モールの脅威にもたいしてその手のうちもわかっていて、あえてラインアウトでは競ってこらずモールに備えたのだが、その過程で多くの反則(オフサイド)を繰り返してしまっている。アドバンテージを許し、トライを許し、イエローを受けてしまう。
ジャパンはBマレイへの対策、モール対策、はじめから解っているこのこの2つの対応の執行能力の不足から2つのトライを許している。
一方ウェールズのディフェンスからは何ふり構わぬ必死さが伝わってきた。高温多湿の疲労、怪我人が続出して、満身創痍の中で肝心なところで集中力を発揮できた。
第五の違い ゲームの組み立ての違い
ジャパンは前回勝てたのと同じようなゲーム運びを想定した。つまり、前半はキックなどをつかい先制点をとられてもあまり差をつかずに追いかけて、ウェールズが疲れる後半に一挙にすスピードアップをして逆転するというものである。
一歩のウェールズにはそんなことを考える余裕はなかった。序盤キックをつかうのは良いが最後は行けつところまで行くのだということが見えた。
結果的にはほぼそのとおりであった。しかし違っていた部分がある。それは、ウェールズの踏ん張りで、ウェールズのフィジカ的な足がとまるような時間帯がきても、なんとか精神力で保っていたことであった。
そしてそれがラスト5分での9点差に引き離すトライを産んだことになる、
「冒頭であと5分あればジャパンの2連勝はできた」と記したが、これがそのまま、ジャパンのゲームの流れの読み間違い、集中力をあげ、ギアをかえるタイミングを柔軟に変えることができなかったことをそのまま示している。
つまるところ、ジャパンは首脳陣のインテリジェンスは素晴らしいのだが、その実行能力にまだ若干かける部分があったの対し、ウェールズは作戦の立てようがない中で出たメンバー必死になってプレーした点で、わずかに上回ったということである。
その必死の頑張りが、疲労がプレーに影響する時間帯を後ろにずらすことになり、ウェールズの集中力で75分にトライを生むという微かな余力を残してしまった。
ウェールズの精神力を挫くタイミングは、何度かあったと思う。例えば59分ディアンスののトライの後のコンバージョンは勝負どころだった。トライのあと私はこれで7点差、少なくともこのゲームは引き分けに持ち込めると期待した。しかし、コンバージョンがはずれてしまう。次にライリーのトライ&ゴールでも2点差がついたままとなった。
序盤にあっさりとウェールズの先制を許してしまうというのもいかがなものか、た序盤にジャパンが先制、追加点を上げれば、もっと早くウェールズの戦意を挫くことが出できたと思われる。それができない場合のプランBとして消耗戦のプランBを遂行しても遅くはなかったのではないだろうか