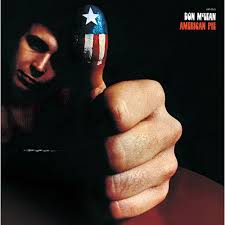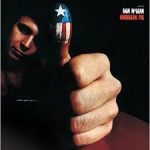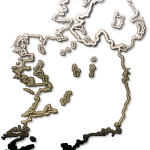総括のまえに、書き忘れた点が何点かあったので、ここに忘れずに記しておきたい。
1,補足その1 「堤防が壊れる時」
大ヒットした、レッドツェッペリンの4枚目の最後の曲に「レヴィー・ブレイク」というブルースの曲がある。この邦題では全く意味がわからないが、原題は「 When the Levee Breaks」なのである。つまり「堤防が壊れる時」。
歌詞は
If it keeps on rainin', levee's goin' to break If it keeps on rainin', levee's goin' to break When the levee breaks I'll have no place to stay 雨が降り続くなら 堤防は決壊する 堤防が決壊すりゃ 居場所はなくなる
このアルバムの発売は1971年11月。「アメリカンパイ」の発売とほぼ同時期である。
アメリカンパイでは「堤防」はまだ乾いているが、ツェッペリンはその堤防がこわれたらどうなるのかを歌っている。(この歌詞は古いブルースから借用したものであるのが後から明らかになっている)
これは関連性があるのだろうか?「アンサーソング」なのだろうか?ちなみに本シリーズの(その3)で指摘したように同じアルバムのなかの一曲には「THE BOOK OF LOVE」という歌詞も出てきている。そして、その曲の題名は単純にストレートに「ロックンロール」なのである。ツエッペリンにとっては珍しいノーテンキな曲なのである。
これらは100%偶然であるに違いない。場所もニューヨークとロンドン離れている。
偶然なのは解っている。しかし、わたしには、そこに象徴的な意味を感じざるをえない。
2,補足その2 マドンナと映画の「アメリカンパイ」
2000年にマドンナがこのアメリカンパイをカバーし、リバイバルヒットさせた。。マドンナ主演のコメディ映画「二番目にしあわせなこと」のテーマ曲である。ここではじめてこの曲を知った人たちも多いと思う。
ただし、マドンナのバージョンはオリジナルの導入部と1番と最後の6番しか歌っていない。
つまるところ、60年代に音楽が死んていく(=古き良きアメリカかがなくなっていく}という、この曲のいちばん重要な部分をバッサリと省いてしまっている。アメリカ音楽の暗い歴史や、思わせぶりの暗喩など小難しいことや知的な遊びなどは不要というわけだ。これこそ、アメリカ根底に流れる「反知性主義」の現れであると考えられる。
このように中核部分を省いてしまうと、まさに青臭い青春の「童貞ソング」にもなってしまう。童貞コメディの「アメリカンパイ(1999年)」にもピッタリである。
この映画のほうも大ヒットで続編が何本もつくられている。シモネタ映画でどれもまったく酷い映画であるが、こういうのがアメリカでは一般受けするのである。そしてアメリカではヒットし金儲けしたもの勝者で勝者が正義なのである。
3,補足その3 1962年という年について
ドン・マクリーンは1945年生まれ、新聞配達をしていた「音楽の死んだ日」の当日は14歳であって、2番の歌詞のある高校のプロムで失恋した少年(大人になりきれない孤独な暴れ馬のような少年)のころは17歳のころ=1962年と考えられる。(17歳はライ麦畑のホールデンと同じ年齢であり、他にも多くの共通点が伺われる。この点は後述したい)
この1962年という年は、古き良きアメリカを象徴する年である。
アメリカングラフィティ、ヘアスプレイなどなどのミュージカル映画。
すべて舞台は1962年である。
ビートルズらによる、ブリティッシュインベンションの前である。これ以降 キューバ危機、ケネディ暗殺や、公民権運動、ベトナム戦争などとなっていく。明るく愉快なアメリカは、悩める大国アメリカになっていくのである。
ホイチョイの馬場氏が1962年を舞台にした映画を紹介することで、そこところを上手に説明してくれているので、下記動画をぜひご覧いただきたい。
1962年にもどりたい。そんな想いは、アメリカの高齢者だけでなく、映画や音楽を通じて、若者世代にまで広がっているのである。
その想いが、MAGA運動を押し出し、今のトランプ政権を生み出したといっても過言ではない。