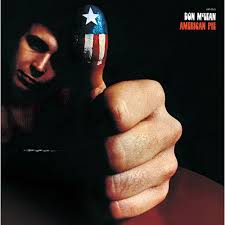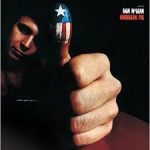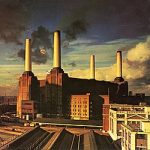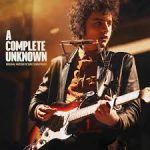アメリカンパイには様々な暗喩が散りばめられている。今回はその3として、ハイテンポで軽快に歌われる2番と3番をまとめて解釈し直すこととする
目次
1,2番 その1 「the book of love」,について
まずは歌詞の全体を確認しよう
曲はいきなりハイテンポになり、それを合図に2番の歌詞が歌い出される。2番では50年代後半の2つのヒット曲がうまい具合に歌詞の中に入っていて、2つのヒット曲その歌の印象が思い出され、歌詞にに深みや洒落っ気を含ませることに成功している。
Did you write the book of love, And do you have faith in God above, If the Bible tells you so? Do you believe in rock ’n roll, Can music save your mortal soul, And can you teach me how to dance real slow? 君が「愛の本」を書いたのかい 至上の信心でも在るのかい 聖書が教えたのかい ロックンロールを信じるのかい 音楽は魂の救済となるのかな 君はゆっくりなダンスを教えてくれるのかな
Well, I know that you're in love with him 'Cause I saw you dancin' in the gym You both kicked off your shoes 君は彼のことを好きなんだ 体育館でダンスをしてるのを見てわかったよ
歌詞を聴くと宗教的でキリスト教に絡んでいるようでもある。
「the book of love」と言えば、聖書のことである。
「the book of love1957年に黒人コーラスのモノトーンズがヒットさせた曲である。歌詞を確認する。
(I wonder, wonder who, who-oo-ooh Who wrote the Book Of Love?) 愛の本を書いたのは誰なんだろう Tell me, tell me, tell me Oh, who wrote the Book Of Love? I've got to know the answer Was it someone from above? 教えて教えて 誰が「愛の本」をかいだの? 答えを知りたい 天国の誰かのか
この最後の「someone from above?」のとこをもじって、アメリカン・パイでは「do you have faith in God above,(天の神の信心があるのか}となっている。「the book of love」が聖書のことだということの洒落である。
モノトーンズのヒット曲では中間部に、「愛の本」の目次が歌われる
(Chapter One says to love her You love her with all your heart Chapter Two you tell her You're never, never, never, never, ever gonna part In Chapter Three remember the meaning of romance In Chapter Four you break up But you give her just one more chance) See upcoming rock shows Get tickets for your favorite artists 第一章 彼女を愛せよ 心から彼女を愛してる 第二章 彼女に告げよ 決して決して別れることはない 第三章 ロマンスの意味を思い出し 第四章 別れを告げる だけど彼女にもチャンスを与える 今度のロックコンサート、お気に入りのアーチストのチケットさ
「愛の本」は「愛の顛末まで」書かれている。全ての恋ハッピーな顛末とは限らない。しかし、彼女を引き止める最後のチャンズは、ロックコンサートに誘うこと=「音楽の力」は、愛の顛末を変えるえてしまうのだ。
「Did you write the book of love,」の歌詞を知った上で、話を本題のアメリカンパイにもどそう。
Well, I know that you’re in love with him `cause I saw you dancin’ in the gym. You both kicked off your shoes. 君が彼が好きだとわかったよ 体育館での君らのダンスを見てさ ふたりとも靴を脱ぎすて、おどってもの
この時代アメリカの高校生の週末は体育館でのダンスパーティーの催しがあった。
高校時代の狙いの彼女とはうまく行っていなようである。どうも、うまく行かない筋書きの「愛の本」を描いたのは狙いの彼女本人だったようである。でも「the book of love」の歌詞にあるように、「音楽の力を信じてる」のでラストチャンスにかけようとしていのだ。
高校生っぽくてキュンとする。
2,2番その2「pink carnation and a pickup truck」 について
アメリカパイの歌の続きはこうなる
Man, I dig those rhythm and blues I was a lonely teenage broncin' buck With a pink carnation and a pickup truck But I knew I was out of luck The day the music died リズム・アンド・ブルーズにはまってたな ボクは孤独で暴れ馬みたいな十代だった。 ピンクのカーネーションとシボレーの小型トラックがあったけど でも運はなかったことなのさ 音楽が死んだ日だったんだ
ここで2曲めのヒット曲を示唆する歌詞の「ピンクカーネイション」が登場する。この歌はMarty Robbins の1957年のカントリーヒット曲 A White Sport Coat (And A Pink Carnation)である。
歌詞の一部を紹介する
A white sport coat and a pink carnation I'm all dressed up for the dance A white sport coat and a pink carnation I'm all alone in romance 白いスポーツ場にピンクのカーネーション ダンスのためにびしっと決めて 白いスポーツ場にピンクのカーネーション ロマンあふれる場所で俺はひとりぼっち Once you told me long ago To the prom with me you'd go Now you've changed your mind it seems Someone else will hold my dreams ずいぶんと前に君は俺に言った 俺と一緒にプロムへ行ってくれると でも君は考えを改めたようだね 他の男が俺の夢を奪ったんだ
「 prom =プロム」は高校で行われるダンスパーティーのこと。白いスポーツのコートは学校の運動場のこと。高校のダンスパーティーで、ビシッと決めていったのに彼女をゲットできなかった寂しさを歌っている。まさにマクリーンにとっては、10年前の苦い思い出そのものである。
曲の「アメリカンパイ」ではこの曲のイメージが錯綜する。「ピンクカーネーション」では白いスポーツコートでの失恋だが、「アメリカンパイ」では、場所が体育館はになる。共に、青々しい寂しさをが溢れてくる。
「I was a lonely teenage broncin’ buck(僕は孤独な暴れ馬の10代だった)」カーネーションは儚さや優しさを感じられ、ピックアップトラックは対極的な荒々しさを表す。したがって、10代のころの情緒が定まらない不安定な精神状態にあったことを表している。まさしく「 lonely teenage broncin’ buck」である。
But I knew I was out of luck
The day the music died
だけど、幸運にはみはなされていた。
音楽が死んだ日だったんだ。
つまり、好きな子は他の男子といい関係になってしまっている
ということは、好きな音楽が、その価値を失ってしまった=この日も音楽が死んだ日の一つになったということである。
でも、どこかに強がっているようにも感じられる。
なんだか、「ライ麦畑」のホールデンのようでもある。
(このほかにも、ライ麦畑との共有点がある。この点は別途言及したい)
そしてお決まりのコーラスが流れるのである。
2,3番その1「the jester」はボブ・ディラン
Now for ten years we've been on our own And moss grows fat on a rollin' stone But that's not how it used to be When the jester sang for the King and Queen In a coat he borrowed from James Dean And a voice that came from you and me 10年間俺たちのやり方でやってきた 転がる石にも苔はつく でも昔のようには行かない 王や女王のために道化師は歌った ジェームス・ディーンから借りたコートを着て 君やボクからの声だった
Now for ten years we’ve been on our own
And moss grows fat on a rollin’ stone
But that’s not how it used to be
日本国歌「君が代」の歌詞は、細石の苔のむすまで」だが、「moss grows fat on a rollin’ stone」は格言、「転がる石は苔むさない」のもじりであると同時に、ボブ・ディランの楽曲「Like a rollin’ stone」のことでもある。64年のアルバムに入っている。
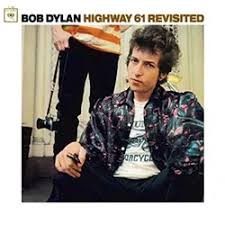
歌詞の一部を紹介する
How does it feel How does it feel To be on your own With no direction home Like a complete unknown Like a rolling stone? どんな気分だい どんな気持ちなんだい 独りぼっちになるっていうのは 家路もなく 知り合いすらいない 転がる石のようになるのはさ?
つまり、ドン・マクリーンのバンドも10年同じやり方でいやってきて、根無し草のようだったが、それに苔が付きてきたということは 少しは芽がでてきたということなのだろう。この同じやり方とは50年代の踊れる軽いアメリポップのスタイルだと思われる。でもそんな時代錯誤の音楽は他に誰一人やっているものがいない。一人ぼっちだ。
ボブ・ディランが「転がる石になるってことはどんな気分だい」ということの答えで、10年やれな苔もはえるさ(少しは金になったきた)という答えなのだろう。洒落てる。
「In a coat he borrowed from James Dean(ジェームス・ディーンから借りたコートを煽って)とは、ボブ・ディランの2枚目のアルバムのジャケットのことであある。当時付き合っていた恋人のスース(映画ではシルビイという名前はとなっている)とイーストブレッジを寄り添って歩いている姿であるり、たしかにジェームス・ディーンばりの上着を羽織っている。つまり、ボブ・ディランのデビューしたてのころを歌っている。

すでに60年代に入っていてディランも大ブレークなのに、ボブ・ディランは50年代を代表する若者のカリスマだった、ジェームス・ディーンのようなコートを羽織っているというところの皮肉もある。
When the jester sang for the King and Queen(道化師が王と王妃のために歌ったとき)」。なぜ、ボブ・ディランが「the jester」なのかと言えば、このころボブ・ディランは「サーカスでギターを習った」とか、「サーカスで街を回っていた」などといった謎めいた発言が多かった。映画「名もなきもの」の中でもエピソードが出てきる。また後になるが、1975年の「ローリングサンダーレビュー」ツアーでは、サーカス団のよう一座を引き連れてまわり、自らも白塗りで道化師の雰囲気をにじませている。
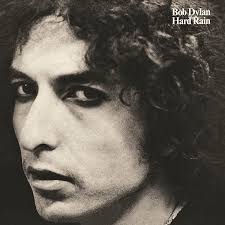
歌詞は前後するが、ここに出てくる「 the King and Queen」 と誰なのかも色々取り出さされてきた。
マーチン・ルーサー・キングだとか、ケネディ大統領だとかの解釈も在る。しかしそれは60年代後半にはいってからでである。
この時期60年代初期の音楽会はフォークリバイバルの時代であった。この時代のキングはピートシーカーでクイーンはジョーン・バエズとであると考えるのが。大御所のウッディガスリーは年老いて病気で入院中である。ジェスターことボブ・ディランはまだ生ギター一本で、ピートシーカーのニューポートフォークで歌い。ジョーンバエズと一緒に「悲しきベイブ」を歌っていた。その後ピーターポールアンドマリーやバーズなどもディランの曲をカバーして大ヒットとなる。
「And a voice that came from you and me(君と僕から声)」。この時期のボブティラン、「風に吹かれて」「戦争の親玉」などの反戦歌や「くよくよするなよ」など「僕たち若者の素直な声」を代弁していた。
Oh, and while the King was looking down The jester stole his thorny crown The courtroom was adjourned No verdict was returned 王が下を向いたすきに 道化師は王のトゲトゲの王冠を盗んだ 裁判は延期され 評決は答申されなかった
ここでの王は、前と同じくピート・シーガーと捉えるのが自然である。
つまり、フォークリバイバルがマンネリ化した間に、その大座をうばって大スターになったということである。ピートシーカーは下を向いていた。つまり、歌うことよりは、マネジメントやイベントなどの事務仕事に忙しかった。
一節には。「ここでのキングは、キングオブロックンロールのエルビス・プレスリーである」というものもある。確かに、プレスリーは除隊後のこの時期、下を向いているように元気がなく、やる気のないドーでも良い映画などに出演していた。
何れにせよ、その「キングの座」はボプディランが奪ったのである。ディランは、一躍音楽会のトップに立った。
しかし、歌詞では「stole his thorny crown(王冠を盗んだ)」となっている。物騒な表現だ。これは実は、ボブ・ディランの歌詞やメロディラインには、常に盗作の疑いが付きまとまっているからである。現在でもそうである。
また、ピートシーカーのニューポートフォークフェスディバルで、そのステージをロックに変えてしまった。ここでもステージを、またピートシーカーが積み上げてきたフォークの牙城を奪ってしまったのである。
「The courtroom was adjourned No verdict was returned(裁判は延期され評決は差し戻された)」
このように裁判用語が出てくるのも、ディランの盗作騒ぎの関連で続いているのである。いまだに賛否両論あり結論はでていない。
4,3番その2 ビートルズ
And while Lenin read a book of Marx The quartet practiced in the park And we sang dirges in the dark The day the music died レーニンがマルクスの本を読んでいるとき 4人組のバンドが公園で練習していた ボクたちは暗闇で葬送曲を歌った 音楽が死んだ日に
『Lenin read a book of Marx(レーニンがマルクス読んでいた)」のレーニンはジョンレノンのこととされる。現在のアップルミュージックでの歌詞はLeninではなく明らかにLenonとなっている。それではジョンレノンはマルクスの本を読んでいるとは一体どういい意味なのか。
jジョンは、資本主義の時代で搾取されてる労働者階級出身である。ビートルズの初期の頃は、R&Bやストレートな曲が主流だったが、中期になると、前衛的、確信的になってくる。この時点では、まだ本を読んでいるだけで政治的な活動の実践はしていなかった。ということだろう。
レボルーション
You say you want a revolution
Well, you know
We all want to change the world
You tell me that it’s evolution
Well, you know
We all want to change the world
毛沢東語録を持った紅衛兵たちの活動を皮肉った曲である
ビートルズの公園といえば「ストロベリーフィールズ」である、ジョンやポールが少年時代をすごしたリバプールにある。
公園で練習していた4人組、ビートルズである。ビートルズの公園といえば「ストロベリーフィールズ」である、ジョンやポールが少年時代をすごしたリバプールにある。練習していたとは、ライブ活動をせずにレコード作りに没頭していたことを表してると思われる。
すでに中期のビートルズの楽曲は軽く踊れるような曲ではなくなってきている。
このようなエルビスの中だるみ、ディランのエレキへの転換、ディランの盗作騒ぎ、、ビートルズの音楽の変化、ライブ活動の停止、ジョンレノンの政治的志向などなど。
これらすべてが、音楽が死んだ日の一つであって、60年代は50年代の古き良きアメリカが失われていくことを表している。