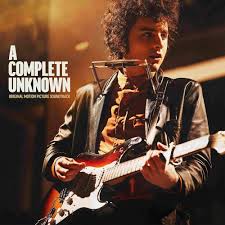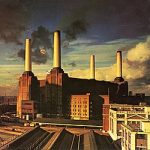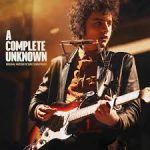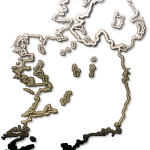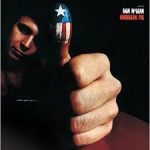目次
1,はじめに
不気味な曲である。
ベース音が半音ずつさがって、すすり泣くようなハモンドがロングトーンを鳴らし続ける。
そして常識ではない意味不明な歌詞がこれでもかと続く様は凄まじい。ミスター・ジョーンズに常識では考えられないような、自分では身に覚えのない不思議で、不条理なことが次々と発生する。それはなにかの予言や予兆かもしれない。まるで、カフカや、村上春樹の小説のようである。そうなら、村上春樹の主人公なら「やれやれ」と行って受け流してしまうこともできるのだろう。しかし、小説ではない。羊はでてこない。自分の身に起きる不確実な可能性が否定でないのので、聴くものを恐怖のどん底に引きづりこむのだ。
2,1番 鉛筆をもって部屋に
You walk into the room with your pencil in your hand
You see somebody naked and you say, “Who is that man?”
You try so hard but you don’t understand
Just what you will say when you get home
Because something is happening here but you don’t know what it is
Do you, Mr. Jones?
あなたは鉛筆を手に持ち部屋に入る
あなたは裸の人を見とめる「だれなんだ」
とても難しすぎて理解できない
家に帰ってなんと言おうか
You walk into the room with your pencil in your hand
「あなた」が「鉛筆をもって部屋に入る」。
「あなた」とは誰なのか、この時点で「あなた」の性別や職業などの言及はない。また鉛筆という言葉が唐突に出てくる。鉛筆をもって部屋に入るというのだから、普通の生活で鉛筆を使っている人なのだろうと想像できる。学生なのか作家なのか画家なのか、作家ならタイプライターをつかうだろうし、学生なら、ノートブックを持ってという文になりそうである。しかしそうでなく間違いなく、「鉛筆をもって部屋にはいる」のである、しかもその鉛筆はあなたの持ち物なのだ。ほんとうに鉛筆なのだろうか?もしくは他のモノの象徴なのだろうか?
You see somebody naked and you say, “Who is that man?”
ところがそこにだれかしらない裸の人がいる。まだ性別は分からないが、あなたが「Who is that man誰なんだ」と言うことで、ここで初めて「裸のだれか」が男だったことがわかる。「あなた」この言葉は疑問文だが、裸の男に尋ねているのではなく、自問自答をしているのだ。
普段使っている部屋になにげに入ったところに、見知らぬ裸の男がいたら、それはびっくりだ。現代なら「セクハラ行為」だ。中居正広問題の第三者委員会報告でのとんねるずの石橋が六本木のホテルのスイートルームでやらかした行為と同じである。まだこの時点では、「あなた」が、男性なのか、女性なのかはわからない。あなたとは「私」かもしれない。ただし、セクハラ行為はあなたが男性なのか女性なのか関係ない。
You try so hard but you don’t understand
Just what you will say when you get home
「理解しようとしても難しい」そりゃそうだろう。普段使っている部屋に突然見知らぬ裸の男がいたら、混乱しないほうがおかしい。
また「家に帰ってなんと言おうか」ということのなので、この出来事が、昼間、家のそとの出来事であったこともわかる。ホテルか職場なのだろう。そして家には、何も知らずに待っている同居人が居るということも解る。つまり「あなた」は表面上はまっとうな普通の人なのだ。
And something is happening here but you don’t know what it is
そして何かがここで起きている だけどあなたにはわからない
この曲に繰り返し出てくるこの1行がすべてを言い表している。明らかに非常的な何かが起きているの確かだ。
Do you, Mr. Jones?
図星だろ ミスター・ジョーンズ
最後に ズバッと死刑宣告のように、「あなた」を特定した名前が明確に告げられる。まさしく、コナンや古畑任三郎のような名探偵がドラマ終盤に真犯人を告げるようがごとくにだ。ズバッとだ。聴衆は「あなた」が「私」ではなかったことには一安心だが、逆にジョーンズは私の隣に座っているの人かもしれない。この聴衆のなかにそのジョーンズさんが居るんだ。そう思うと恐怖を感じざるをえない。
作詞の構成がさえている。説明的なところは一切なく、客観的に淡々と語られ、聴衆はその謎の中に引きこまれていく。そして ジョーンズさんの名前が高々と告げられる。その衝撃波の威力ににたじろいでしまう。
3,2番 部屋での会話
2番では部屋にいる見知らぬ裸の男とジョーンズ氏の会話は描写される。なんと、驚くことにジョーンズ氏はそんなに混乱はしていない様子なのだ。見ず知らずの裸の男と会話ができるのだ。つまりこの部屋についての何かを何かをしっているようなのだ。なにかを期待してこの部屋にはいったように思える。しかし、その期待は達成できなかったのである。
ジョーンズは何を期待していて、何が達成できなかったのか、またここで新たな謎が発生する。
You raise up your head and you ask, “Is this where it is?”
あんたは顔を上げて尋ねる「ここがそこなのか?」
顔を上げて尋ねるのだから、その前は顔を伏せていたことになる。期待とちがって落ち込んでいるのか、もしくは、メモかなんかを見ていたのかもしれない。今度はSAYでなく、ASKなので、尋ねた相手は、見知らぬ裸の男ということになる。
「ここがそこなのか」ということは、やはり部屋での何にかを期待していたのだろう。そこには裸の男ではなかったなにかがあったはずなのだ。
And somebody points to you and says, “It’s his”
「見知らぬ男」があなたを指さして言う
「これは奴のものだ」
また謎である。裸の男の返事が噛み合わない。
あなたを指さして、It’s hisとなる。指さしているのだから、Itは「あなた」ということになる。となると、「あなた」はここでは人間でなくモノになっているということだろうか。そうであれば、「あなた」という肉体としての入れ物を指しているのだろう。もしくは体の一部を指さしたのか?そして、「あなたは彼のものだ」の彼が誰かという新たな謎がでるが、それよりも衝撃的なのは、私の体が私のものではないということを告げられるのだ。
And you say, “What’s mine?” and somebody else says, “Well, what is?”
あんたは言う「俺のはどれだ?」、別の奴が言う「え、何がどこにあるって?」
そんなことを告げられた「あなたジョーンズ」は、何が私の体なんだと言い返す。
確実にその部屋にはもうひとり見知らぬヤツが居るのだ。somebodyとsomebody else は別人だと考えられる。きっと前の文節に出てくる彼とはsomebody elseのことだろう。そいつは「あなた」のその質問をはぐらかしてしまう。
となると、ジョーンズ氏の肉体は、他のだれかさんのモノになってしまうということだ。このあと、ほかのだれかさんとジョーンズ氏の肉体との間で、ホモセクシャルな性的肉体関係が持たれるのだろう。
ということは、1番のYou walk into the room with your pencil in your hand
のpencilはペニスのことである可能性が出てきた(スラングで pencilはペニス)。そうなるとなんと、ジョーンズ氏も最初から裸であったことになる。
And you say, “Oh my God, am I here all alone?”
あんたは言う「なんてことだ、俺はここで一人ぼっちなのか?」
そういう解釈ならばこの一文もぴったりはまる。つまり、期待していたのは売春婦でノーマルなセックスだったのに、場違いな部屋に入ってしまったということだ。
But something is happening and you don’t know what it is
だけど何かが起きている そしてあんたにはわからない
何かが起きているのは確かだが、「超自然的な何か」ではなさそうである。ジョーンズ氏の行動を知り尽くしている誰かが裏にいて、ジョーンズ氏をはめようとしていると思われる。
Do you, Mr. Jones?
そうだろ? ミスター・ジョーンズ
4.3番 見世物小屋で骨を
2番では見世物見物のジョーンズさんに、だれかが近づいて骨をわたす。
You hand in your ticket and you go watch the geek
Who immediately walks up to you when he hears you speak
And says, “How does it feel to be such a freak?”
And you say, “Impossible!” as he hands you a bone
あなた(ジョーンズ)はチケットを手に、見世物見物に行く
彼はあなたの声を聴くやいなや近づいてくる
そしてこう言うんだ「どんな気分だい、変人になるのは」
骨をわたしながら
あんたはこう言う「無理、無理、無理」
(How does it feelはライク・ア・ローリング・ストーンの歌詞の一部である。)
ジョーンズが芝居を見に行った際に、
だれかが近づいてきて、骨をわたす。
骨を渡す人物はだれなんだろう、裸の男がいる部屋にいた誰かではなく、見世物小屋の出演者だろう。ジョーンズを陥れようとしている影の集団は、ジョーンズのことを知り尽くしているのだから、ジョーンズが見世物小屋に行くことはお見通しのことであり、骨は見世物のジャグリングでつかう小道具なのだろう。グルである出演者はジョーンズに飛び入りで出演させ怖い目に合わさうとしているのだ。
5,さび 木こりの役割
もうここでの「あなた」は、ジョーンズさんのことである。ワタシでないだけは安心だ。ジョーンズはそんな不思議な体験をしているのだから、木こりとのコンタクトをとっているといっても不思議ではない。木こりを知っているのは鉛筆と関係が在るのかもしれない
You have many contacts among the lumberjacks
To get you facts when someone attacks your imagination
あなたは沢山の木こりの知り合いがいる
あなたの想像を攻撃する現実を突きつける
その木こりは誰かがジョーンズさんの想像を否定しようもんなら、現実に引き戻してくれる。ジョーンズが想像癖があるのだろう。やはり、作家や画家なのかもしれない。木こりたちには何らかの借金や借りがあるのだろう。
But nobody has any respect,
世の中の誰も尊敬などしていない
anyway they already expect you to all give a check
To tax-deductible charity organizations
慈善団体に減税のための小切手をきるのを期待しているだけだ
ジョーンズ氏は、作家にしろ画家にしろ、作品は適当に売れて成功しているらしい。その作品や、だれからも尊敬されるようなことではなさそうである。
世知辛い現実は間違いなく作動している。
事前団体への小切手という普通のPOPSには似つかわしくない畏まった言葉をあえて持ち出すとで、聴衆は一瞬でリアリティに引きもどされる。このばかげた話は決してフィクションでないのだ。一流の作詞能力だ、うまい。
6,4番 エスタブリッシュなジョーンズ
ジョーンズがいわゆる知識階級のエスタブリッシュの一員であったことが過去完了形で語られる。仕立ての良いスーツを着て高級腕時計などもついけていそうである。その成功にはある程度ルッキズムも反映したのだろう。ねじまき鳥の渡辺昇のようでもある。
Ah, you’ve been with the professors and they’ve all liked your looks
With great lawyers you have discussed lepers and crooks
You’ve been through all of F. Scott Fitzgerald’s books
You’re very well-read, it’s well-known
あなたはあなたの見た目を気に入った教授達と一緒だった
お偉方の弁護士とあなたが、らい病患者や詐欺(問題)の議論をした
あんたはフィッツジェラルドの著作をすべてを読んだ
あなたは見識者としてよく知られていた。
出てくるたとえがすべてエスタブリッシュメントのそれらしい。
教授たちとの交流、詐欺や差別と戦う正義派の弁護士との活動、文学にも精通し、フィッツジェラルドも全て読破している。博識であることも知られている
But something is happening here and you don’t know what it is
だけど何かが起きている そしてあんたにはわからない
Do you, Mr. Jones?
そうだろ? ミスター・ジョーンズ
そんなエスタブリッシュなジョーンズに、本人の関知しないところで魔の手がさして待ってくるのだ。
7,5番 喉のレンタル
Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels
He crosses himself and then he clicks his high heels
And without further notice, he asks you how it feels
And he says, “Here is your throat back, thanks for the loan”
今度は剣を飲み込む男がやってきて、彼はひざまずき
十字を切って ハイヒールをカチッと鳴らすと
それ以上の予告も無く、あんたにどんな気分か尋ねた
そして彼は言った「あなたの喉をお返しします。貸してくださってありがとうございます」
見世物小屋の続きらしい
剣を飲み込む男が登場し、跪いて、十字をきってヒールの高い靴をクリックし
予告もなく行為を喉を貸してくれてありがとう、
ジョーンズさんは、ステージに上がらされ、剣を飲み込まされたのだ。(もちろん、トリックは当然在るはずだが)。ジョーンズはそうつな恐怖を味わったに違いない。
「裸の男」以外にも、次から次に不思議で不条理なことが起き、混乱させ、不安を雑談させる。包囲網は徐々にせまっているのである。
And you know something is happening but you don’t know what it is
何かが起きている だけどそれが何かあんたにはわからない
Do you, Mr. Jones?
そうだろ? ミスター・ジョーンズ
8,6番 一つ目小僧登場
こんどは一つ目小僧が登場する、二人の会話は噛み合わず、質問すればするほどなぞが広がっていく。最後には牛にされてしまう
Now, you see this one-eyed midget shouting the word “Now”
And you say, “For what reason?” and he says, “How”
And you say, “What does this mean?” and he screams back, “You’re a cow!
Give me some milk or else go home”
「今」叫ぶ一つ目小僧
「なんでなんだ?」と問えば、「どうして?」と答え
「その意味は?」 と問えば
「あんたは牛だ」と答える「ミルクをくれ、でなければ失せろ」
一つ目小僧。これも見世物小屋のできごとなのかもしれない、さもなくはジョーンズの見る幻聴の可能性もある。言葉はすれちがい、全く会話がなりたたない。ナンセンスだ。アリスのハンプティダンプティのようだ。
一つ目小僧は、日本ではメジャーな妖怪である。欧米での1つ目の怪物といえば、ギリシア神話のホメロスのオデュッセイアにでてくるキュークロープスのポリュペーモスであるが、こちらは巨人で小男ではない。「なんでもない」という偽名にだまされてしまう。どちらも怖くはなく、ちょっとユーモラスな印象であることが共通点。ここにでてくる1つ目もどことなくユーモラスである。
And you know something’s happening but you don’t know what it is
何かが起きている だけどそれが何かあんたにはわからない
Do you, Mr. Jones?
そうだろ? ミスター・ジョーンズ
9,7番 駱駝のように
Well, you walk into the room like a camel, and then you frown
You put your eyes in your pocket and your nose on the ground
There ought to be a law against you comin’ around
You should be made to wear earphones
あなたは、ラクダのように部屋に入ってきて、眉をひそめる
ポケットに自分の目玉を詰め込み、鼻を地面につける
あなたがうろつくの取り締まる法律があったらな
イヤホンをつけるべきだった
ラクダのようにとはどんな姿勢なんだろう。駱駝の習性なんて一般的に知られているわけではない。
実はここに来て駱駝が登場することで、この歌が、新しい価値への順応や創造にたいする対応に関係した歌であることが判明する。
ニーチェのツアラストラにはこうある
「人の精神は 駱駝→獅子→小児と変化する。」
これは新しい価値を見つけるステップである。
駱駝の精神とは重い荷物を背負った駱駝が砂漠を行き来するように、なすことに疑問を持たずにただ繰り返す状態
獅子の精神とは、獅子が自分の意思で獲物をえるように、「我なすべし」としてなんとなく新しい価値への挑戦をする段階
そして最後に小児の精神になる、忘却であり、精神的に自由でありこの段階で自分の意思を意識することができるのだ。新たしい価値に染まることが可能になる。
このニーチェによれは、最初にジョーンズ氏が、部屋に入ってきた時には、まさに駱駝の状態で、新しい価値観にふれようともしていなかった状態であるということになる。
You put your eyes in your pocket and your nose on the ground
眼をポケットにしまい、鼻を地面につける。
鼻を地面につけるのは前足を降りただんだ駱駝の仕草を思い起こさせる。「眼をポケットにしまい」はニーチェのように新しい価値観への窓を自ら閉ざしていると解釈できる。
There ought to be a law against you comin’ around
あなたは、そんな未熟な精神状態のまま、場違いの見世物小屋なんかをうろついている。そこにいるすでに小児の精神状態になっている者たちにとっては目障りだ。
You should be made to wear earphones
「イヤホンをつけるべき」とは、ジョーンズは駱駝の段階なので、イヤホンで新しい価値を遮断すべきだったということだろう。もしくは美術館の音声ガイドのように、懇切丁寧にまずは駱駝から椰子の実になるようにガイドをつけるべきだという意味だろう。
‘Cause something is happening and you don’t know what it is
何かが起きているからさ そしてあんたにはわからない
Do you, Mr. Jones?
そうだろ? ミスター・ジョーンズ
10、まとめ
最後のバーズで駱駝=ニーチェがつながることで、この曲は、現体制にどっぷり使った保守的(=自分が保守的とも認識していない)人たちにとっては、理解できないような出来事が次つぎにおこっている状態なんだ。「時代は変わる」と同じだと言ってよい。ということが確かになる。
60年も前の曲なのに今の時代にもピッタリなのでゾッとする
現代に置き換えれば、ウクライナ戦争、トランプ現象、欧州の極右の台頭。60年代後半から今まで、リベラルで平等な世界を理想として当たり前にただ漠然と生きてきた人、自分を革新的でリベラルだと思いこんでいる人こそが実は保守的になっているのだ。外界の変化を理解しようとしないにとっっては、ジョーンズ氏におこった奇妙な出来事と見えるだろう。(それは不安で不気味である。そう思うのあなたは、駱駝の状態になってはいないか。眼をポケットに入れてしまってはいないだろうか。良きにつけ悪しきにつけ、時代は変わっていくのだ。警笛は鳴らされている。少なくとも。水かさは増してきている。
10、おまけ その後のジョーンズ深読み
ジョーンズ氏の名前がこの曲のあとにどのように扱われているのかをまとめておきたい。
■ジョンレノン:
ホワイトアルバムの2枚めの2曲めのヤーブルースにこのジョーンズ氏がまんま登場する。明確にディランのジョーンズである。
I feel so suicidal
just like Dylan’s Mister Jones.
Lonely, wanna die.
すごく自暴自棄な気分で
まるでディランのミスター・ジョーンズ
孤独だ、死にたい
■ビリーポール Me and Mrs. Jones
ビリーポールの1970年の代表曲、つくったのはヒットメーカーのギャンブル&ハフのコンビとCary Gilbert。3週連続の1位を記録。
ここではジョーンズ氏の奥さんと私との不倫関係が描かれる。ディランの曲との関係は不明だが、人目を忍んでホテルのカフェで手を握り合う熱烈な関係であり。もしもその夫が何ひとつわかっていないディランのジョーンズだとしてもおかしくないし、ありえる話であり、そんな創造をもしてしまう。
■クール&ギャング Jones VS Jones
80年の大ヒットセレブイレーションの2曲め。こちらはまったくディランとは関係がなさそうだが、さらに深読みをしてしまうと面白い。
こちらは、スタイリッシュな軽いのりだが、ジョーンズ夫妻の離婚話である。
Cause I received a notice
They called me on the phone
To come and sign the papers
Of Jones vs. Jones
Gone are the days of me and you
知らせを受け取った、電話が来た
離婚届にサインをと
ジョーンズ対ジョーンズ
二人の日々は終わった。
こうならべると、偶然なのかジョーンズという名の人生は問題だらけである。
■缶コーヒーボスの宇宙人ジョーンズ
日本で一番有名なジョーンズは、CMに登場する宇宙人ジョーンズである。宇宙人ジョーンズは地球外から、地球人の生活の調査のためにおくりこまれて、特に日本を中心にさまざまな職業を転々とし、有名人ともふれあって、次から次に理解し難い不思議な体験をする。まさにディランのジョーンズの周りに起こっているが如く。演じているのはトミー・リー・ジョーンズで本名での出演だ。
「このろくでもない、素晴らしき世界」のキャッチフレーズは、ディランのシニカルなユーモアの世界とどこか共通するものがある。
■心の哲学 セラーズの思考実験「ジョーンズの神話」
心の哲学は現代の哲学で、心と体の関係いわゆる「心身問題」をとりあうかう分野である。それは心は体は別の実体なのか一部なのかというような問題であり、私という存在はいったいどこにあるのかがなどが論じられている。
そのなかでセラーズ博士は、その著書『経験論と心の哲学』において「ジョーンズの神話」という思考実験を提案している。
それによれば、ライル人という心的な問題の概念を持っていない人種を想定する。ライル人は心を認識しないのでブツブツ口にだして行動する。ジョーンズ氏もそんなライル人の一人である。ライル人のライルは行動主義(心は泣くとか笑うとかの行動であるという立場)を取ってる研究者の名前。普通のライル人は行動することによってのみ自分の意思を認める人種だ。そんな中、ジョーンズは静かに知的活動をおこなう特殊なライル人を発見する。そしてなぜそうできるのかを理論つけようとする。ライル人は最初は例えば泣くことで自分の内的感情の変化を発見するが、行動によらず一人称としての自分をどうして発見できるのかを、段階を踏んで理解しようとする。そんな自分も発見していく。
ライル人のジョーンズも、不思議な世界の変化にさらされているのだ。
ディランのジョーンズ氏は不思議な体験の不安の中で、私というものがどこに在るのか分からなくなってきている。出会う人達は全くの無感情で淡々と行動するだけのライル人のようである。こちらのジョーンズ氏はどんどん自分というものがなくなっていくようでもある。