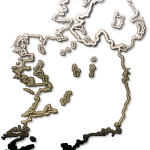1,十二支縁起とは
十二支縁起とは、仏教において人の苦悩の元となる事柄がどこからくるのかということを12の段階からの因果関係から解いたものである。これにより人は生まれながらに苦しみを背負っていちものであるとする。したがって、この苦しみこそが人そのものであるとも言える。修行によって悟りにいたれば、これらの苦しみからは開放されるのだとする説明としてつかわれている。
この12の段階とは順に、「無明」、「行」、「識」、「名色」、「六処」、「職」、 「受」、 「愛」、「有」、「生」、「死」の12個である。
大乗仏教では三毒(貪欲:欲望をむさぶる、 瞋恚:いかりやにくしみ 愚痴:無知、おろかさ)の3つの悪事が無明という中にすでに存在しているのだという。
2,脳科学との共通点
このブッダの教えは、現在最先端の脳科学におけるニューロンの動きからくる人の行動や精神作用の説明と全く同じプロセスであることが指摘されている。つまり、カオスからニューロンの発火がつながりあって次第に自己組織化がおこり、ある形におさまって行動や意識となってまとまるのである、それが行動や記憶や意思や性格や人格などを形成していくプロセスのパターンである。つまり、人そのものである。
そのように考えると2500年前の東洋の知恵や思考が2500年の時を経て正しいということが証明されつつあるといえるのだ。
各段階の意味とつながりをもう少しく詳しく言えば、下記の通りでる。
「無明(むみょう)」:混沌としていて過去のさまざまな苦がごちゃまぜにある状態。カオスな状態である。
「行(ぎょう):指向性のこと、物事がそのように向かうこと、意思の作用
つまり混沌の中から何らかの指向性がまず産まれる
職(しき):識別作用 洞察力や見極めというと
意識の向かった先が何かが見定められる
各色(みょうしき):その形態や名前などのこと。名と姿である。
見定めたものが何かがわかりだすようになる。
六処(ろくしょ): 現代科学では5感だが、仏教では六つの感受機能、感覚器官。即ち、眼耳鼻舌身意の6感官のこと。
ここで人間の感覚機関が働きだす
触(しょく):この段階で、6つの感覚器官が外界と接触する
受(じゅ):この段階で6つの感覚器官がその情報を察知する
愛 (もしくは憎):溺愛。その情報が好ましいか好ましくないかを見極める。 ニューロンの発火がパターン化してくる
取(しゅ):物事に執着しどうしてもそれが欲しくなる、やりたくなう(もしくは避けたくななる)
有(う):それらが形をもった存在となる。愛や憎しみや欲望などの対象となる。
ある程度のアトラクターができる
生(しょう):産まれる。ただし、それは思うがままにならない。ここで愛や憎しみが形となって産まれ、妬み悩みなどという崩し難い形になる。だから人は苦しみを背負って生まれてくるものである。脳科学で言えば、ここでニューロン発光のパターンがアトラクターとして自己組織化する
死(し) ここでは死亡でなく物事が完結するということである。脳科学ではニューロン発火のパターンが自己組織化によってある形をとることで固まってしまうことになる。つまり悩みや苦しみならそれは悩みや苦しみとして心に若まりとして残り続ける。
このような複雑系からの自己組織化の動きは、自然界にも存在する。ランダムな空気の流れが竜巻になったりするのである。またそれらは最新の量子物理学の考えにも準拠している。量子力学の紐理論でもクオークなど物の根本は形の定まらない「ひも」のようなもので、確率としてだけ存在して、それらが自己組織化によってある形を形成しているのと考える。
3,ループ構造とフラクタル構造
この12段階のプロセスの考えをリンゴをみつけて食べるという行為で考えてみる
最初はなにか混沌としているのだが、なにか満たしたいという指向性や欲求があらわれ、食べるものを探すという意思が形成される。そこで視覚、臭覚、聴覚、味覚、触覚などの6感が働き眼の前のりんごを見つけ出す。そのりんごは美味しそうか食べられそうかななどを見極めることで、はじめて、そのりんごが私の食欲を満たす対象としての存在となる。そしてその林檎を手にし食べて完結する。しかし人間として食べてはいけないりんごであることもある。そうなるとその林檎は存在はしているが、私にとっては存在しないものとしなければばらない。「有」以前は動物の本能的な動きであるのに対して「有」以降は人間特有の意思や理性、倫理など抑制する脳の働きとなる。したがってそこに悩みや苦しみが存在してくる。
仏教ではこれらをこのように因果関係として直線的に考えるのだが、脳科学ではこれらをループとして捉える。いったんおさまるがそれらは新たな混沌となり、また同じプロセスが始まるのである。
また、これは大雑把な行為をなぞっただけであるが、それぞれの事柄のなかに同じようなループ構造の脳の働きがフラクラル構造のように存在する。例えば、りんごを知覚するだけも、視覚機能のニューロンが過去の記憶のニューロンを刺激し反応しあって、混沌の空間から指向性によって意図や形を見定め、りんごという存在を認識するというループのプロセスからの自己組織化が必要である。さらにその中の要素であるリンゴの姿を察知するというところにも同じようなループ構造が存在する。そしてさらに…..
4,ラグビーで言えば
ラグビーで言えば、まず因果関係としいぇはこれはアンストラクチャーからトライが産まれる、もしくはノートライに終わる。というプロセスを表したものと全く同じである。
即ちアンストラクチャーという「混沌」とした状態から何らかの最初の動き(指向性=行)が「バタフライエフェクト」となって、15人の動きがなんの決め事もなく自由に動くことで、パスがつながっていくという自己組織化がおこり、最終的にはその自己組織化の結果、芸術的なトライが生まれたりするのだ。その自己組織化のまでの過程のなかで、お互いのニューロンの発火を刺激し合うように、15人の選手の5感(6感)が働き、信号をチャッチし別なニューロンの発火につながる。それはあたかも空中を美しい軌道をえがいて行き来する楕円球のパスと同じようである。
そしてそのトライはともかく美しい。なぜ美しいかといえば、そのトライは偶然ではなく、自己組織化によって美しい形になるように導かれていくからなのである。
しかし、そのような美しい形で完結するばかりではない。そのなかで様々な「煩悩」が邪魔をしてしまう。それはある形まで行ってもノックオンやタッチや反則で中断する。しかしその瞬間、アドバンテージルールによって、そこに新たなカオスが出現するのである。そこにカオス=死があるからこそ、またカオスからの新しい自己組織化が始まっていくのである。
そしてそられのフラクラル構造も考えられる。
ラグビーボールがどちらにころぶかというひとつのきっかけが、混沌を生み出し、混沌から個々の選手の動きが自己組織化してですばらしいプレーやトライが生まれ、それらが形成されてゲームという形になり、ゲームは勝ったり負けたりをする。さらに、自信をもって作り上げたチームも一個の敗戦でまたカオスの如く混沌となってしてしまうことがある。その時からまら新たなループが始まるのである。それは苦しみでるが成長でもある。まさにフラクタル構造である。
人間は変わっていく存在である。カオスの状態がないと次のループは始まり得ない。いつも同じ思考パターンや行動パターンにハマっていれば次の高みに登るループにはあがれず、ただ悩んでいるだけで成長がないことになる。
カオス、無明、混沌、挫折、瓦解、そしてラグビーゲームでのぶざまな敗戦。これらの存在意義もそこにあるのではないだろうか?