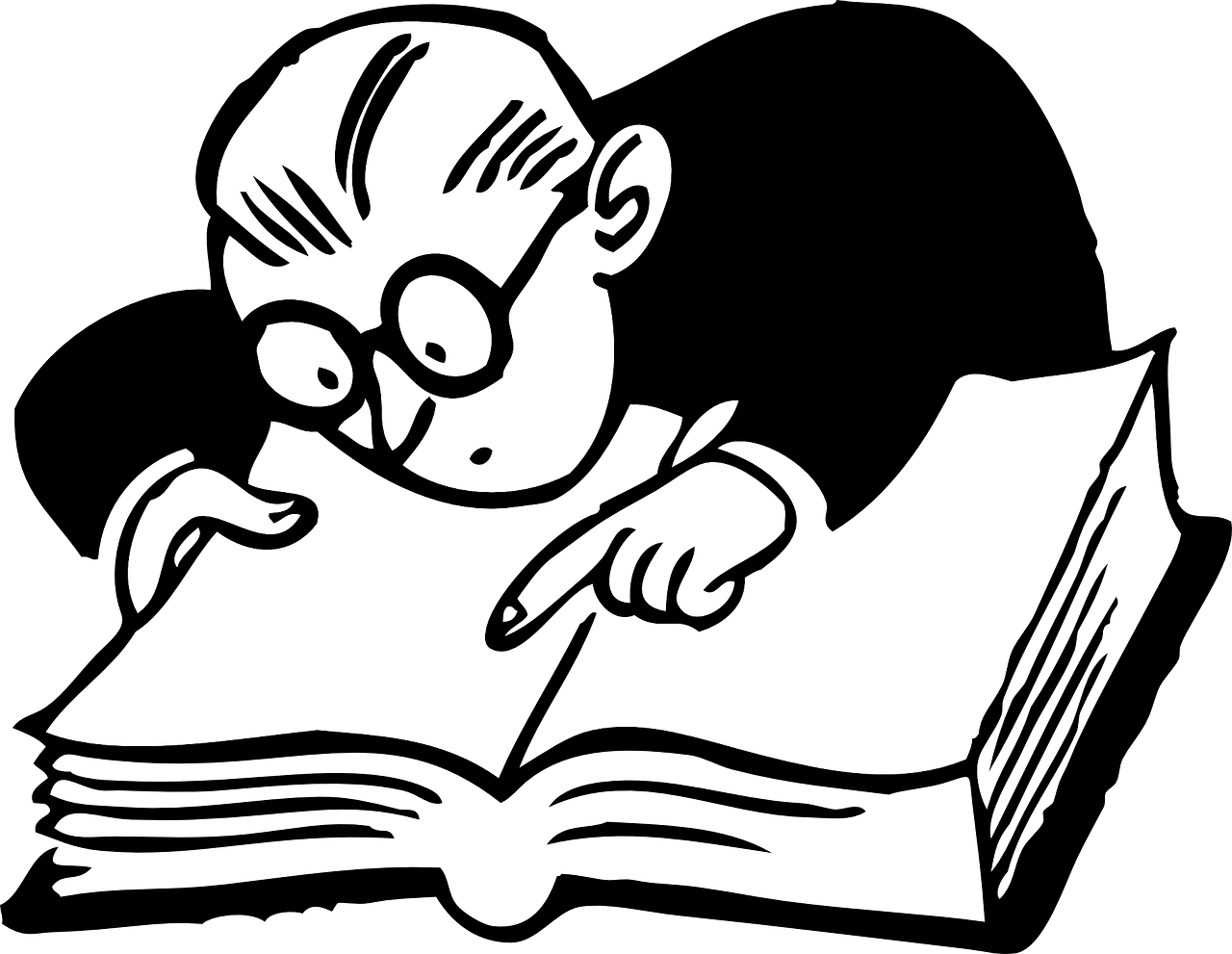2025年はノックオンがノックフォワードとなり、ゴールラインがトライラインという呼称に統一されるなどのエポックメイキングな年になった。これにかかわらず、ラグビーでは時代により新しい言葉が出たり消えたりしている。そこで、最新の言葉だけでなく参考としてに過去の言葉もできるだけ拾い上げ、ここに ラグビー現代用語の基礎知識を全面的に改定する。
あいうえお順にはじまり、5月までの完成を目指す。ある程度の段階で都度、公開はするがその後も都度加筆や修正をおこなう。履歴は残さない。
目次
- コウコウラグビー 高校ラグビー (文化)
- コウコウニホンダイヒョウ 高校日本代表 (チーム)
- コウベセイコウ 神戸製鋼 (チーム名) コベルコ神戸スティーラーズ
- コーチ coach (役職) コーチング coaching (トレーニング)
- ゴール goal (ルール)
- ゴールキック goal kick(ルール)
- ゴールポスト goal Post(グランド)
- ゴールライン goal Line(グランド)
- ゴールラインドロップアウトgoal Line drop out(ルール)
- コクリツ 国立競技場 (スタジアム)
- コバヤシシンロクロウ 小林深緑郎(人物)
- コマザワ 駒沢オリンピックスタジアム (スタジアム)
- ゴメーターライン 5metl line( グランド)
- ゴメータースクラム 5metl scram(ルール)
- コラプシング collapsing (ルール)
- コリジョン collision(スキル)
- コンテスト contest (スキル ルール)
- コンテストキック contest Kick(スキル、戦術)
- コンバートconvert(ルール) コンバージョン conversion goal (ルール)
- コンバート convert(ブランド)
コウコウラグビー 高校ラグビー (文化)
日本の高校生のラグビーのこと。頂点は全国高等学校ラグビー大会(通称花園)である。(参考 花園)
コウコウニホンダイヒョウ 高校日本代表 (チーム)
花園が1月に終了すると、高校の日本代表チームが結成されて、海外に遠征することが通例になっている。
ここに出場できれば、ラグビー選手として、高校日本代表の称号を得ることができる。
コウベセイコウ 神戸製鋼 (チーム名) コベルコ神戸スティーラーズ
神戸に拠点をもつ古豪のラグビーチームである。林、大八木、平尾、イアンウィリアムス、さらには元木、堀越などスター選手が揃い、日本選手権7連覇を達成した。その間 三洋電機(パナソニック)との名勝負を繰り広げた。しかし7連覇達成の決勝戦の数日後に震災に見舞われ、グランドが液化現象の被害にあるなどしたが、選手たちはこぞっれ復興のボランティアを行った。
現在はプロチームとしてコベルコ神戸スティーラーズ
コーチ coach (役職)
コーチング coaching (トレーニング)
コーチとは馬車で馬が引く4輪の車両のことである。それは乗る人をその人が目指す目的地に安全に運ぶものであである。スポーツの指導者は上達を目指す人をその目的に届けるという意味から、そういう役目を果たす人をコーチとよぶようになった。
昭和までの日本ではその意味でのコーチという文化はなかった。ラグビー界でも、スパルタやシゴキ、体罰など理不尽な指導が行われていたという過去がある。スポーツ全般は体育の一貫として行われ、自主的に楽しんで行うものといったスポーツという文化もなかったことも根底にあった。
最近は指導も細分化させ、各チームには様々な分野のコーチが採用されている。
ヘッドコーチ
アシスタントコーチ
FWコーチ
BKコーチ
アタックコーチ
ディフェンスコーチ
S&Cコーチ
メディカルコーチ
ゴール goal (ルール)
トライ後のキック(コンバージョンキック)で、キックしたボールがクロスバーを超え、Hポールを超えれなばゴールごなり、2点が追加される。
ポールに当たっても内側に転がればゴールとなる。
ゴールキック goal kick(ルール)
ゴールポスト goal Post(グランド)
ラグビーのゴールポストはH型、高さ3.4m以上、横幅5.6m、地面からクロスバー上端部までの高さは3m
長らく地面と当時にゴールポストにボールがつけられればトライが認められていたが、下記の理由でそれが認められなくなった。
ゲームの際に安全対策としてゴールポストの周りに緩衝材が巻かれている。したがって旧ルールでは緩衝材の厚みだけゴールラインは近くなることになる。これを不当としてゴール前のディフェンスの際にこの緩衝材を剥がしてしまうチームが乱立してしまった。安全上の対策から必要なので、旧ルールは廃止になり、ゴールラインに接地するか超えなければトライが認められなくなった。つまり、ゴールラインの長さは緩衝材を巻いた2つのポール幅だけ短くなったことになる。
ゴールライン goal Line(グランド)
2025年の名称統一の通達で、ゴールラインはトライラインに呼称が変更になった。(ゴールポストの項も参照)
そもそもそこを超えてもゴールでなくトライが認めらられるだけだったので、ゴールラインという呼称は合理的なものではなかった。しかし、名称にゴールと言う名称のつく反則やルールがたくさんあり、スムーズな呼称変更が進むかは注目である。
ゴールラインドロップアウトgoal Line drop out(ルール)
2024年のルール改正で導入され、2025年の名称統一でトライラインドロップアウトに名称変更になった。
(関連 グランディング)
コクリツ 国立競技場 (スタジアム)
現在の国立競技場は2020東京オリンピック開催に合わせて、旧国立競技場を立て直したもの。座席数68000人。
実は立て直しに関しては、さまざまなすったもんだがあった。もとは当時のラグビー協会会長森喜朗のツルの一声で、2019年ラグビーワールドカップに合わせて8万人規模の立て直す計画であり、12年にはデザインコンペでイラク出身のデザイナー、ザハ・ハディード氏の案が採用された。しかし斬新なデザインだったものの高額な建築費がかかることが後にあきらかになり、当時の首相の安部晋三の決断で、ゼロベースでデザインから見直すことになった。最終的には現在の隈研吾デザインの形で決定したが、2019年W杯には間に合わなかった。2020年オリンピックもコロナ禍のために1年延期となりさらに無観客での実施となった。
ワールドカップでの使用を断念する経緯にかんして、当時の文科大臣と、森元総理の間で意見の食い違いがあり、その溝は現在まで埋まっていない。
旧国立競技場では平成7年まで1月15日に日本選手権の決勝が行われ、晴れ着姿の若者が散見できるなど冬の風物詩であった。ラグビーの歴史的名勝負が行われている。特に昭和後期から平成にかけての早明戦は毎回超満員となるプラチナチケットとなった。
旧国立競技場の伝説的な名勝負として下記が挙げられる
1982年12月 早明戦 観客数66999名の動員記録となる
1985年1月15日 日本選手権 新日鉄釜石7連覇を達成。松尾雄治引退
1987年12月 いわゆる雪の早明戦
1995年1月 神戸製鋼7連覇達成。その数日後に神戸は震災に見舞われる
2013年12月 旧国立での最後の早明戦 松任谷由実が登場し数曲を歌う
コバヤシシンロクロウ 小林深緑郎(人物)
日本のラグビー文化の発展に寄与した重要人物の一人。1949年生まれ2024年逝去。立教大学卒業後、商社マンとなるも海外ラグビーの虜になる。インターネットなどない時代に短波ラジオで現地のラグビー中継にのめりこんだ。2003年、ベースボール・マガジン社から出版された『世界ラグビー基礎知識』は、ラグビーファンのバイブルとなった。(当然この『ラグビー現代用語の基礎知識』も小林へのリスペクトでオマージュである)。
Jスポーツでも解説者として活躍、晩年は村上晃一と掛け合いなどで、話の途中で不思議な間があくことなどがあったが、そこがまた人気であった。2007年ワールドカップで、カナダ戦での大西翔太郎の同点ゴールが決まった際に「オーバーーー」と叫んだ話は伝説となっている。
「トライライン」という連載を毎月ラグビーマガジンに執筆していた。期せずして、ゴールラインがトライラインという名称に変更になった2025年からは、トライラインという言葉を聞く度に小林のことを思い出すことになるだろう。
コマザワ 駒沢オリンピックスタジアム (スタジアム)
正式名称は 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
世田谷区にある、陸上陸上競技場。1964年の東京オリンピックの際に関連のスポーツ施設とともに建設された。
現在はリコーブラックラムズが本拠地として使用している。収容人員は2010人。最寄り駅は田園都市線の駒沢大学駅から徒歩15分ほど
ゴメーターライン 5metl line( グランド)
タッチラインの内側5mと、トライランの内側5mにあるライン。双方とも破線で引かれている。タッチラインに並行する5メーターラインは、ラインアウト時にライアアウトを形成するのに使う。ラインアウトはその5mラインと15mラインの間で行われる。投げ入れたボールが5mラインを超えなければ、やり直しか相手ボールスクラムになる。
トライラインに並行な5mラインそのラインとトライラインの間で起こった反則やミス、タッチなどの再開の際にすべて5mライン上から再開する。したがって。5mラインからゴールラインまでの間でのスクラム、ラインアウト、GK、フリーキックは存在しない。
ゴメータースクラム 5metl scram(ルール)
キャリーバックの際の再開方法である。上記のように5mライン上で攻め込んだ側のボールでのスクラム再開となる。
トライランドロップアウトのルール採用によって、この5メータースクラムの発生頻度は少なくなった。つまりディフェンス有利になっている。
コラプシング collapsing (ルール)
collapsコラプスとは崩れるということであり、ラグビーでのコラプシングはモールやスクラムを崩す行為として危険なので反則となる。ただしスクラムでのコラプシングの判定は毎回微妙であり、崩れた時にその原因がどちら側にあったかで判断される。レフリーにより主観や印象によって左右されると言っても過言ではない。
コリジョン collision(スキル)
コリジョンはぶつかり合うことである。ラグビーではぶつかりあった際の接点のことをコリジョンという。コリジョンでどちらが優位に立てるかはゲームの勝敗に大きく影響する。
コンテスト contest (スキル ルール)
コンテストとはボールの確保を競い合うという意味である。タックル、スクラムやラインアウトの際はもちろん、モールやラックでの密集。タックル成立後のブレイクダウンの際などに奪い合いがおきる。コンテストの結果で相手の反則やターンオーバー、ジャッカル(スティール)、モールアンプレアブルになればボールの所有権を奪ったことになる。
高校生以下のラグビーでは安全上下記のコンテストは禁止されている。高校生はスクラムは5m以上押してはならない。中学生以下のスクラムはノンコンテストである。ミニラグビーでは、高学年のラインアウトはコンテストありだが、リフトは禁止となる。中学年のラインアウトはコンテストも禁止となる。
コンテストキック contest Kick(スキル、戦術)
キックは相手にボールを渡してしまうことが多くなるが、あえて高くボールを蹴り、落下地点に走り込ませ落ちてくるボールの確保を競い合わせる。このキックのことをコンテストキックという。キックオフの際などでも活用できる。
コンバートconvert(ルール)
コンバージョン conversion goal (ルール)
コンバージョンの日本語の意味は変換するとか取り替えるという意味である。例えば、野球などで選手の配置を替えることをコンバージョンという。そう考えると、ラグビーのゴールがなぜコンバートなのかは不思議といえば不思議である。下記のような仮説がなりたつと思うのだが、いかがなものだろう
昔のラグビーではトライは0点でゴールを狙う権利を取得するというだけで、ゴールが決まって初めて得点になったということは知られている。したがって、トライという行為をゴールキックという行為に返還するということでコンバージョンという言葉が使われているのではないだろうか
コンバート convert(ブランド)
かつて大阪に本社のあったラグビー用具の専門メーカー「株式会社うしとら」のブランド名で後に会社名となった。スパイク、ボールなどを提供していたが、2011年に倒産した。倒産後も在庫分は花園近くの店で販売していた記憶があるが、現在は不明。ギルバートなどが日本に入ってくるまで、日本の昔の皮のボールはほとんどコンバートだった。