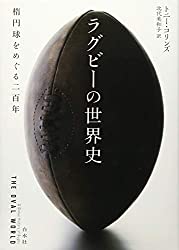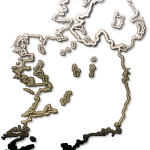ラグビーの世界史 楕円球をめぐる200年 トニーコリンズ著 北代美和子訳 白水社
この本は英国の歴史家である筆者が、200年に渡るラグビーの歴史をまとめたものです。460ページにも渡る大作。とてもアカデミックな内容なのに、まるで小説を読んでいるような情緒あふれる文章、読み進むうちに筆者のラグビー愛をひしひし感じることができ、一気に読破してしまいました。もちろん、日本ではこれまで全く語られていなかった史実や真実を数多く知ることもできます。
このシリーズでは、この本の各章をネタバレにならない程度に追って紹介して、その史実の持つ意味を考えてみたいと思います。
第一回 序章 少年と楕円球
第二回 第一部 キックオフ
第三回 第二部 5カ国対抗に向けて
第四回 第三部 ラグビーを世界へ
第五回 第四部 嵐迫り来る中の黄金時代
第六回 第五部 両大戦下における挑戦と変化
第七回 第六部 ラグビーの新たなる地平
第八回 第七部 伝統と変化
第九回 第八部 21世紀へ
第十回 終章 ラグビーの魂
今回は第一回 序章 少年と楕円球 です。
序章では、筆者が中学一年生のとき、ラグビーの虜になったある出来事が鮮やかに描かれます。その時以来、筆者はラグビーというスポーツの持つ多くの謎にも直面し、それが一人の少年をラグビープレーヤーでなく歴史家としての道に歩ませたのでした。そしてその40年後に「この本」となって結実するのです。
この本は2011年ごろ出版されたので、残念ながら2011年のブライトン、2019年のW杯というさらに世界史を覆す出来事には触れられていません。
少年コリンズに訪れたある出来事の部分を引用します
1973年の夏だった。僕は12歳になったばかりで、中学一年の一学期が始まって、数週間が経っていた。(中略)
コリンズ少年は、当時ラグビーの知識がありました。そしてそれは学校での人気者になれる条件の一つでした。胸を躍らせ体育のラグビーの授業に臨みます。
女子はぼくらを人気者に祭り上げるだろう
僕はプランを練った。スクラムハーフの僕が、スクラムの足元からボールを拾い、右側に立つスティーブ(親友)にパスを投げると見せかけて、スクラムとタッチラインの空間を抜ける。 (中略)
試合開始10分、敵のゴールラインから25ヤードのスクラム。僕らのプランが始動。がら空きのゴールラインがぼくに手招きをしていた
けれども加速しようにもゴールラインは近づいてこない。足が重くなり、脚は短くなったみたい。右側に動きを感じー(中略)二人の重さを受けて崩れ落ち、息つまらせた。
「ノックオン」体育のマイルス先生が言った。
僕は泣きそうになった。
そのことは、筆者のコリンズ少年にプレーヤーとしては向かないと意識させることになります。しかし、それ以上にコリンズ少年はますますラグビーの魅力にとりつかれた。さらに、ラグビーの不思議な謎に非常に興味を持つことなります。
その時、コリンズ少年にとってのラグビーの謎とは
「なぜドイツやブラジルではサッカーなのか」 「世界中ではサッカーなのに、この街はラグビーなのか」 「人数の違う二つのラグビーがあるのは何故」
そして序章の最後を筆者はこう締めくくっています
「1970年のどころんこのグランド それが語る物語、それが答える疑問、それが解決しようとする謎は、(中略)ラグビーを見たことのあるすべての人の頭に浮かぶ謎だ」 (中略) 『ラグビーとは、僕らが暮らす世界とそれがどうやって創られたかの歴史である」
このコラムを読んでいる方は、ラグビーの魅力にとりつかれている方と思います。それぞれがラグビーとの出会いがあり、それぞれが、その場面を覚えているのではないでしょうか?
(私もこの筆者と同じような経験があり、その瞬間の記憶が45年ぶりに蘇りました。高校時代体育の授業で、ロック(ポジションのロックではなく音楽のロックです)少年だった私は、体育の授業は大嫌いでありました。しかし、ある日体育の授業でのその瞬間ラグビーの魅力に取り疲れたのです。それはボールが私に渡った瞬間、そして目の前に相手がいなくゴールラインしか見えない瞬間でした。それは胸の奥底から自然に沸き起こった何かで、動物的、肉体的、本能的何かであり、しかし、ただ単純に前にボールを持って走るということの動作でしかありません。無我夢中で走ったのを覚えてはいる、確かトライになったはずですが、トライを取ったことよりも自分にもそんな本能的な部分があることに、感覚的な驚きを覚えました。それがラグビーでした。)
(その後、ラグビー少年からロック少年に戻ってはいましたが、ある時、またラグビーの魅力にとりつかれました。それは秩父宮の芝と青空のコントラストを見た時でした。
私の話をつい長々書いてしまったは、この歴史書の序があまりも素晴らしい文章なので、私の心の奥底に持っている記憶を思い起こさせれてくれたからでした。この序章を読んだだけで、この本がただの歴史書でないことが容易に想像できます。)